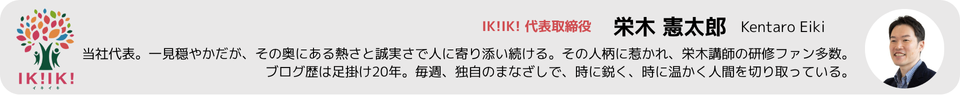昨日(8/23)、10年前まで勤めていた会社の課の同窓会に参加しました。
そこで再会したのが、今でも尊敬する上司の一人です。
この上司を一言で表すなら「厳しい人」。
- 明確に結果を求める
- 結果を出さない部下には容赦ない
- めったに褒めない
- 甘えを許さない
- 自分にも他人にも厳しい
一部からは“鬼軍曹”と呼ばれていました。昭和の匂いがプンプンします。
今なら「パワハラ認定では?」と突っ込まれそうです。
でも、この上司は違いました。
基準が一貫してブレない。
「ここを超えたら怒る、ここまではOK」というラインが誰に対しても同じ。
しかも、プレイヤーとしてもマネージャーとしても結果を出し、最後は必ず自分が責任を取る。
だからこそ、安心してついていけたのだと思います。
上司から「好き嫌い(これはOK/これはダメ)」をはっきり示される方が、(理不尽でなければ)部下は安心する。
筆者はこれこそ“心理的安全性”の根っこだと感じます。
実は、筆者が今の仕事で大事にしていることも、この原体験につながっています。
- 成果への責任:「口先だけ」の人を見てきたからこそ、提供して終わりではなく成果にこだわる。
- 他者感覚:察しようとしない人に嫌気がさしたからこそ、相手視点を大切にする。
- 自分で責任を引き受ける:会社の看板に隠れる人が苦手だからこそ、「会社を支える人」でありたい。
- 先義後利:「利」が先に来るとウソやごまかしが入り込む。だからこそ「義」を先に置く。
最近「厳しい指導ができない上司」「フィードバックがなく成長実感を持てない若者」という声をよく耳にします。
背景には、心理的安全性や多様性を“優しさ”と取り違えていることがあるのではないでしょうか。
心理的安全性のベースは、あいまいな優しさではなく 明確な基準 です。
スポーツも同じ。ルールがあるからこそ自由にプレーできる。
ルールや基準があいまいだったら、かえって混乱を招きます。
多様性もまた、基準があるからこそ違いを尊重できる。
つまり――
心理的安全性も多様性も、その土台は「基準の明確さ」。
あの厳しい上司は、それを体現していたのだと思います。
「優しさ」と「基準」。
この両輪が揃ってこそ、人も組織もイキイキと成長できるのではないでしょうか。
…と、ちょっと真面目に語りましたが、同窓会では結局ビール片手に“鬼軍曹”と笑い合っていたのも事実です。