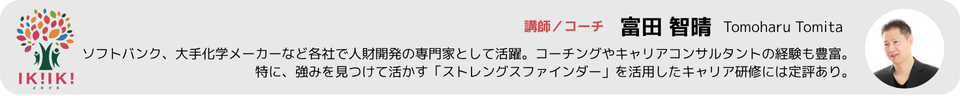コーチングの現場でよく耳にする声があります。
「なんであの人だけ特別扱いなんだろう…」
「評価の基準がはっきりしないから、納得できない」
こうした小さな不満は、職場の空気を重くし、チームの信頼関係を揺るがしてしまいます。
実はこのテーマ、職場だけではありません。
スポーツでは「審判の判定は公平だったのか」が大きな議論になり、政治や経済でも「一部だけが優遇されていないか?」と公平性への疑問が絶えません。例えば、日本の国体(国民体育大会)では、開催県が優勝しやすい”ホストヴィクトリー”の傾向が指摘され、公平性への疑問が投げかけられています。公正なルールや構造が整っていないと、多くの人が「特別扱い」を感じてしまうー。そのことはスポーツの場面でも、職場でも同じなのです。
つまり公平性は、私たちの身近な職場から社会全体まで、共通する大事なテーマなのです。
そんなときに場を落ち着けられるのが、公平性の資質を持つ人です。
まず「みんなが納得できる基準」を大切にし、えこひいきが生まれないように整える。
そのうえで、必要ならルールをよりよく変えていくこともできる——これが公平性の本当の力です。
■「公平性」ってどんな資質?
一言でいうと、「安心できる公正な基準をつくり、そこから変化を動かす存在」。
ルールをただ守るのではなく、納得感をベースにして、変化や改善につなげていける資質です。
■強みと盲点
強み
- えこひいきが生まれない仕組みをつくれる
- 公平な基準を示し、場を安定させられる
- 公平だからこそ、新しいルールへの移行がスムーズになる
盲点
- 公平さにこだわりすぎて柔軟さを欠くことがある
- 人への配慮より「ルールが先」と見られてしまうこともある
■公平性をどう活かす?
・まず「公平であること」で安心をつくる
・そのうえで「どうすればルールをよりよくできるか」を考える
・不公平感を防いでから変化を加えることで、納得感のある改革が進む
・安定から変化へ、段階を踏むことで組織の信頼を守る
■自分らしさを見つけるために
公平性は、ただ「ルールを守る」資質ではありません。
「ルールを守るからこそ、安心して変えていける」——そこに本当の価値があります。
職場でも社会でも「公平さ」が揺らぐと不信感が広がりますが、公平性を持つ人はまず場を落ち着かせ、そのうえで新しい変化を動かせるのです。
「強み」と「盲点ケア」は表裏一体。
公平性を土台にして変化を進めることこそが、自分らしさを輝かせる使い方になります。
「強みを知れば、自分のキャリアはもっと面白くなる。」