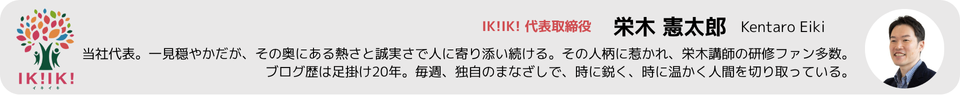朝、目覚ましを止めたあと、まず何をしますか?
スマホを手に取り、SNSやニュースを眺める。
仕事が始まれば、まずメールチェック。
昼休みには気づけば動画を開き、夜は「今日も疲れた」とゲームや好きな食べ物でストレス発散。
――もし「ドキッ」としたなら、それは普通です。
現代の私たちは、今、ひとつの行動を選ぶにも無数の選択肢に囲まれています。
すると、無意識に「ラク」「効率」「おトク」な方を選ぶ傾向にあります。
すると、その積み重ねこそが「不自由」を生むとしらどうでしょう?
「制約=不自由」という常識を疑う
自由とは、やりたいことを好きにできること。
そう思う方も多いでしょう。
でも、それは半分正解で、半分間違いです。
選択肢が多いほど、人は安易な方を選びがちです。
ラクを選ぶほど、挑戦から遠ざかる。
すると今度は面倒なことを避けようとする。
こうして、選択の幅が不自由になっていきます。
やりたいことを好きに選択し続けた結果、「〇〇依存」「〇〇中毒」になってしまい、そこから抜け出せなくなってしまう――
「制約がない」状態は、実は最も不自由なのです。
一見バカげた制約が、自由を呼び戻す
想像してみてください。
あなたが今から遠方から東京まで出張するとします。
普通なら新幹線や飛行機。速くて快適で効率的。
でもあえて、自分に制約をかけて「普通列車だけで行く」と決めたらどうでしょうか。
少しでも効率的なほう、ラクな方、便利な方を選ぶことに慣れた私たち現代人は、このような選択はまずしまいでしょう。
一見、時間のムダに思えます。
松山から茨城まで、19時間の普通列車の旅
実はこれ、最近筆者が実際にやったことです。
朝5時53分、松山駅始発列車に乗りました。
基本的にはスマホやネットには触れず、ただひたすら電車に揺られる旅です。
数えること197駅。
100駅目は、天下分け目の「関ケ原駅」。ちょっと嬉しい気持ちになりました。
つくばエクスプレスの終電に何とか間に合い、研究学園に着いたのは深夜0:40。
身体はぐったりしているのに、心は達成感に満ちていました。
効率を犠牲にしたはずなのに、むしろ「自分の人生のハンドルを握っている」という確かな実感が残ったのです。
「自分への制約」は不自由ではなく、「自由のハンドル」
極端に自分自身に制約をかけた1日。
この旅で学んだこと――
それは、今この瞬間、自分に制約を課すことは不自由を強いるものではなく、本来の自由を取り戻すための“ハンドル”なのだと。
たとえばこんな自由を取り戻すことができます――
0.普段は飛行機や新幹線を使うけど、挑戦心をもって普通列車を使うこともできる。
1.ラクな方を選ぶときもあるけど、いざとなったらキツイ方も選べる。
2.感情を爆発させるときもあるけど、状況に応じて感情を落ち着かせることもできる。
3.ネットやSNSやゲームもやるけど、時間を決めて楽しむことができる。
4.マルチタスクもするけど、一点集中モードにもなれる。
5.ネガティブな思考になるときもあるけど、自分でその思考にストップをかけることができる。
6.普段はSNSやメールで連絡の方がラクだけど、電話や会って話すことも抵抗を感じない。
このように、「極端な制約をかけられる力」こそが、選択の自由を生み出すのです。
自律型人材も同じ原理
これは個人の話にとどまりません。
企業が目指す「自律型人材」も、まったく同じ原理で成り立っています。
自律とは、自ら制約をかけ、目的に沿って行動できる力です。
- SNSをダラダラ見ることもあるけど、学びに時間を使うこともできる
- 短期的な快楽も好きだけど、中長期的な成果を選ぶこともできる
- 誰に管理されなくても、自分を律して動ける
制約をかけるからこそ、選び取れる幅が広がる。
制約をかけるからこそ、自由に生きられます。
AI時代に問われる「極端に制約を選ぶ力」
AIが効率と便利さを「極限まで」高めていく時代。
これはこれで、素晴らしいことだと思います。
一方で、無防備でいれば人間はますます“ラク”に流されていきます。
だからこそ、自らに「極端に」制約を課し、意志力を高めていく人が、AI時代の恩恵を受け「真の自由」を手にできるのだと思います。
極端な制約こそが、ホンモノの自由を生む。
あなたは、どんな「極端な制約」を自分に課しますか?