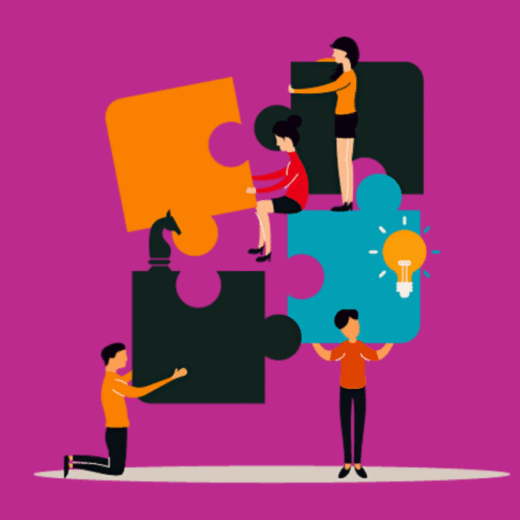
当社は、組織開発(関係の質向上・働きがいのある職場)の支援に関わっております。
その中でお客様からよく聞かれる声は、
「職場を活性化させるために、これまで色んな研修を受けさせたり、施策を取り入れたり、しくみを導入したけれど、なかなか変わらない」といったものです。
業績は悪くないのに、働く人の心はイマイチといった具合です。
これは、世界各国との比較でも如実に表れています。
↓
https://diamond.jp/articles/-/325135
筆者が強く思うこと、それは働く人の「行動パターン」が変わらない限り、真の問題解決につながらない…といったものです。
ちなみに、読者のみなさまは、どのような人と一緒に働きたいですか?
1.そもそも気づかない人・気づいてくれない人
2.気づいても、行動に移さない人(見て見ぬフリ)
3.気づいたら、行動に移してくれる人
どう考えても「3」と答える人が圧倒的に多いと思います。
ですが、今、職場で起きている問題の多くは、「1」「2」の行動パターンを取る人が多いことによって生じています。
「1」の行動パターンが多い人は、指摘を受けると「知らなかった」「聞いてなかった」で開き直ろうとします。
そもそも、気づかないことに問題の原因があることに気づいていません。
「2」の行動パターンが多い人の根底には、「面倒なことには関わりたくない」という心理が見え隠れします。
ですが、困っている人からすれば、「誰も助けてくれない」という孤立感を生じさせ、働きがいを低下させます。
今、日本全体を覆う心理状態のようにも思えます。
「3」の行動パターンの人が多ければ多いほど、一人ひとりが責任感を持って行動し、困難な状況では「助け合い」が生まれてきます。
こうなると、チームの結束力が生まれますし、ミスに気づきトラブルの防止につながりますし、高い実行力で成果にもつながりやすくなります。
これは職場に限らず、チームスポーツや家族など、共同体全般について言えることです。
では、なぜ、日本においては「1」「2」の行動パターンを取る人が多いのでしょうか。
「公共」を気にせず、スマホの画面ばかり見て自分の世界に没頭している人が多い日常の光景を見ると、「確かにそうだな」と思われる方も多いと思います。
A.「公共」「周囲」「利他」
B.「プライベート」「自分」「利己」
という視点で考えると、現代は「B」に偏っているように感じます。
自分で何でも調べられるし、自分一人で楽しめる…といった具合です。
生活のすべてが「自己完結」できてしまうのです。
そうなると、煩わしい(?)人間関係から解放されます。
それが、公との断絶を生み、周囲に関心を持たない…という心理を生んでいるのだと思います。
では、そのような状況を生み出した環境が悪いのか?
と言われると、そうでもありません。
実際にこのようなご時世でも、「3.気づき、行動に移せる人」、つまり、「気配り・目配り・心配りができる人」は現に存在します。
そうなると、これは「環境」のせいではなく、自分の「心の持ちよう(マインドセット)」がその環境を引き寄せている…ということになります。
つまり、組織の活性化に向けては、一人ひとりの「心の持ちよう(マインドセット)」が変わることが大前提にある…ということです。
では、どうしたら「心の持ちよう(マインドセット)」は変わるのでしょうか?
これには様々なアプローチがあると思いますし、正解は1つではないと思います。
その上で、筆者自身の原体験を紹介したいと思います。
筆者は以前、旅行会社の添乗員を務めていたことがあります。
新入社員1年目の私は、よく上司にこんな叱責を受けました。
「栄木、ボーっとしてないで、ちゃんと動け!」
「なんでそんなことも気づけないんだ」
「もっと気働きしろ!」
当時の筆者は、「そんなこと言われたって、言われないと分からないんだからしょうがないじゃないか」と心の中でぼやいていました。
いわゆる「言われないと動けない人」です。
周囲からは、「仕事のデキない新入社員」という烙印を押されていました。
それどころか、「なんで大学を卒業してまで、こんなことやらされなきゃいけないんだ」と思う始末…
20年以上経った今思うことは、当時の筆者は、そもそもの「考え方」と「日常の行動パターン」に問題があったようです。
「損になることはやりたくない。」
「なるべくラクをしたい。」
「自分さえ良ければいい。」
という、典型的な現代人の考え方を持っていました。
また、何でもかんでも理屈をこねて「頭で考える」タイプでした。
(大学で勉強しすぎたせいか(?)少々「頭でっかち」になっていたようです。)
たとえば、駐輪場で自分以外の自転車が倒れていたとします。
当時の筆者は、そもそも倒れていることに気づかず、自分の自転車しか見えていませんでした。
また、倒れていること気づいたとしても、別に自分が倒したわけではないですから、当然通り過ぎていました。
これは、自転車の例に限らず、日常や仕事全般についても言えました。
そんな行動パターンを繰り返していたものですから、当然ながら、「気づく力」も「実行力」も養われません。
それが、上記のような「仕事のデキない人間」につながっていたのだと思います。
そんな筆者でしたが、ある挫折経験をきっかけに「このままではまずい」と一念発起しました。
日常生活において、「気づいたら、ゴミを拾う」という生活習慣を取り入れました。
いわゆる、「3.気づいたら、行動に移す」という行動パターンです。
かれこれ「3」の行動パターンを取り入れてから10年以上経ちますが、それ以降は「気づく力」が高まり、「実行力」のある体質に徐々にシフトしている感覚があります。
結果として、A.「公共」「周囲」「利他」の感覚が以前より備わってきていると思います。
このように、筆者自身が「気づかない・利己」寄りの心の持ちようでしたが、
日常生活において、「気づく➡動く」という小さな習慣を取り入れてからは、徐々に心の持ちようも変わってきました。
そして、その方が人生は楽しい…ということを学びました。
筆者が組織開発の仕事に関わっている根底には、このような原体験があり、これは決して独りよがりなものではなく、普遍的な道理のようにも思います。
実際に、筆者の活動が実を結んだ事例もあります。
↓
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4232/#p4232_04
当社を通じて一人でも多くの方や一つでも多くの組織がイキイキしてくれたら嬉しく思います。


