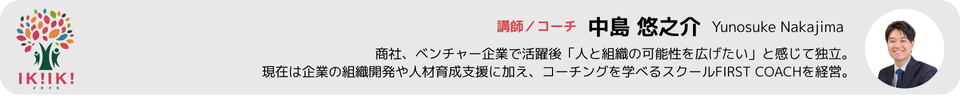先日、自分が経営するコーチングスクールでの授業でのことでした。その日のテーマは「コーチングスキルの実践」。受講生の皆さんは、これまで学んできた知識を実際に使えるようになろうと、真剣に取り組んでいました。
「傾聴のスキル」「質問のフレームワーク」「承認の技法」――
私は丁寧に、体系的に、これまで培ってきたコーチングスキルを伝えていました。受講生の皆さんも意欲的で、ロールプレイでも習得したスキルを懸命に実践されていました。
ところが、一人の受講生がこんなことを言ったのです。
「中島さん、スキルは一通り覚えたつもりなんですが、なんだか相手との間に壁があるような気がして…」
何だろうと思って詳しく聞いてみると、こんな悩みを話してくださいました。
「実際に職場でコーチングを試してみたんですが、部下からの反応があまりよくないんです。習った通りにやっているはずなのに、なぜかうまくいかないんです」
その瞬間、私は「ハッ」としました。
確かに、私自身も過去に同じような体験をしたことがあります。コーチングを学び始めたころ、スキルを覚えることに夢中になり、「正しい質問をしなければ」「適切なタイミングで承認しなければ」と、まるでチェックリストを消化するような関わり方をしていた時期がありました。
相手の話を聞きながらも、頭の中では「次はどの質問フレームワークを使おう」「ここで承認を入れるべきか」といったことばかり考えている。それでは、目の前の人に真剣に向き合えるはずがありません。
その方の言葉は、まさに核心を突いていました。
その後の授業では、受講生の皆さんに問いかけてみました。
「皆さんがコーチングをするとき、本当にその人のことを知りたいと思っていますか?」 「相手の言葉の奥にある本音や想いに、心から興味を持てていますか?」
すると、ある受講生がこんなことを話してくださいました。
「正直、スキルを使うことに集中しすぎて、相手の人となりを見ることを忘れていました。」
別の方からは、
「相手の答えを聞きながらも、頭の中では次の質問のことを考えていました。」
といった声も上がりました。
コーチングを学ぶことで、実は多くの方がはまってしまう“落とし穴”がここにあると感じました。
どんなに高度な質問スキルを身につけても、どんなに洗練された傾聴技術を習得しても、根底に「相手を思いやる心」がなければ、それはただの技術の披露に過ぎません。
一方で、たとえスキルが未熟でも、「この人のことをもっと知りたい」「この人の本当の気持ちを理解したい」という純粋な想いがあれば、それは必ず相手に伝わります。そして、その想いこそが信頼関係の土台になります。
社員一人ひとりと向き合うとき、つい「効率的に」「体系的に」アプローチしようとしてしまいがちです。しかし、人の心は決してマニュアル通りには動きません。
大切なのは、目の前にいる一人の人間として、その人の話に心から耳を傾けること。その人の立場に立って、その人の世界を理解しようとすること。そんな当たり前のことが、実は最も難しく、そして最も価値のあることなのかもしれません。
あの受講生との対話から、私は改めて自分自身のコーチングを見つめ直しています。
「今日のコーチングで、私は本当にクライアントのことを知ろうとしていただろうか?」 「スキルを使うことに夢中になって、相手の心を見落としていなかっただろうか?」
そう自問自答する日々が続いています。
コーチングスキルを学ぶことは確かに大切です。しかし、それ以上に大切なのは、相手に対する純粋な関心と思いやりの心を持ち続けること。
これは、コーチングに限った話ではありません。日常の部下とのやり取り、同僚との会話、家族との時間――すべてに通じる普遍的な真理だと思います。
技術は学べば身につきます。しかし、人を思いやる心は、意識して育てていかなければ簡単に失われてしまいます。
忙しい日常の中で、つい効率や成果ばかりに目が向いてしまいがちですが、時には立ち止まって問いかけてみてください。
「今、私は目の前の人に本当に関心を持てているだろうか?」
その問いかけこそが、真のコーチングマインドを育む第一歩なのかもしれません。