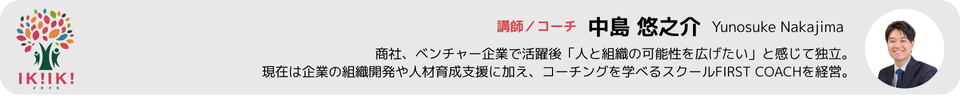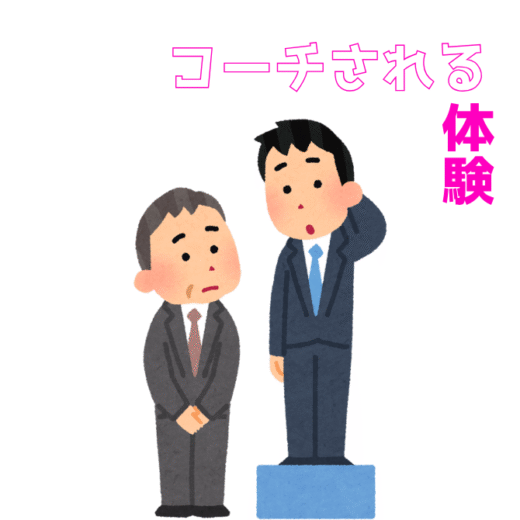
先日、FIRST COACHのスクールに、とても興味深い受講生が入ってこられました。大手銀行で長年人事を担当されていた方で、現在は別の企業の人事部長として活躍されています。
その方(仮にAさんとします)が、初回のオリエンテーションでこんなことを話されました。
「実は、これまで何度もマネージャー向けのコーチング研修を企画・実施してきました。でも、どうしても現場で活かされない。今回は、自分自身がコーチングを受ける体験もしてみたいと思って申し込みました」
Aさんの言葉を聞いて、私は「なるほど」と思いました。多くの企業で、同じような課題を抱えているのではないでしょうか。
「マネージャーにコーチング力を身につけさせたい」 「部下との対話を促進したい」 「1on1の質を向上させたい」
そんな想いから、コーチング研修を実施する。スキルやフレームワークを教える。ロールプレイもする。でも、現場に戻ると結局使われない――。
Aさんは続けてこう話されました。
「振り返ってみると、これまでの研修でマネージャーたちに『こうやって部下と対話しなさい』と伝えてはいたものの、彼ら自身が深い対話を体験したことがあるのか、考えたことがなかったんですよね」
この言葉に、私はハッとしました。
確かに、多くの企業では「マネージャーはコーチングする側」という前提で研修が組まれています。しかし、コーチング技術を身につける前に、まず「コーチングされる体験」「深く聞いてもらう体験」が必要なのではないでしょうか。
泳ぎ方を教える前に、まず水に入って水の感覚を知る必要があるように、コーチングを教える前に、まずコーチングを受ける体験が不可欠なのかもしれません。
Aさんとの個人セッションが始まると、その仮説は確信に変わりました。
普段は部下や同僚をコーチングする立場にいるAさんが、一人の人間として自分の想いや悩みを語り始めたのです。
「実は、最近の組織改革で、長年一緒に働いてきた部下が他部署に異動になりまして…」
「表向きは『会社の方針だから』と言っていますが、正直、寂しさもあって…」
「でも、マネージャーとして、そんな感情を表に出すわけにはいかないと思っていたんですよね」
セッションが進むにつれて、Aさんの表情が変わっていきました。普段は「指示を出す人」「決断する人」として振る舞っているAさんが、一人の人間として自分の感情と向き合い、それを言葉にしていく。
そして、セッション後にAさんがこう言われたのです。
「これまで、部下との1on1で『どう感じているか教えて』と言ってきましたが、自分自身がこうやって感情を言葉にする体験をしたことがありませんでした。これは、想像以上に勇気のいることなんですね」
「そして、こうやって深く聞いてもらえると、意外と話せるものなんですね。ただ、これは普段から相当話せる関係になってないと難しいですね…なるほど。」
Aさんの気づきは、まさに核心を突いていました。
多くのマネージャーが、部下に対して「本音を話してほしい」「もっと相談してほしい」と思っています。でも、彼ら自身が「本音を話す体験」「深く聞いてもらう体験」をしたことがなければ、それがどれほど勇気のいることなのか、どれほど安心感を必要とするものなのか、本当の意味では理解できません。
コーチングスキルを教えることは確かに大切です。しかし、それ以上に大切なのは、「コーチングを受ける体験」を通じて、対話の本質を体感することなのかもしれません。
人は、自分が体験したことしか、本当の意味では他者に提供できないのではないでしょうか。
その後、Aさんは継続的にコーチングセッションを受けながら、少しずつ部下との関わり方を変えていかれました。
「以前は、部下との1on1でも、“聴いている感”を出していました。ただ、思ったよりも彼が本音を話してくれている感じがなくて、やきもきしていました。」
「ただ、今は本音を伝える大変さがすごくわかります。すごく難しいですよね。コーチングの時だけ良い顔していてもだめですね。普段から「この人には話せる」と思ってもらえる状態じゃないと難しいです。」
「そこから、普段の声掛けからちゃんと関係性を作るようになってきました。段々ですが、部下たちも色々話してくれるようになってきた気がします。」
Aさんの変化を見ていて、私は改めて感じました。
マネージャーにコーチング力を身につけてもらいたいなら、まず彼ら自身がコーチングを受ける体験をすることが不可欠かもしれない。
「部下の話を聞きなさい」と教える前に、まず彼ら自身が深く聞いてもらう体験をする。 「部下を承認しなさい」と教える前に、まず彼ら自身が承認される体験をする。 「部下と信頼関係を築きなさい」と教える前に、まず彼ら自身が信頼される体験をする。
その体験があってこそ、初めて部下に対して本物の対話を提供できるようになるのではないでしょうか。
「マネージャー研修を実施したけれど、現場で活用されない」 「1on1の制度を導入したけれど、形骸化している」 「部下からの相談が増えない」
そんな課題を抱えている組織は、もしかするとマネージャー自身の「体験不足」が原因かもしれません。
もちろん、全てのマネージャーにプロのコーチングを提供するのは現実的ではないかもしれません。しかし、例えば以下のような取り組みは可能ではないでしょうか。
マネージャー同士でのピアコーチング(互いにコーチ役・クライアント役を体験する) 人事担当者がマネージャーのメンター役となり、定期的な対話の場を設ける 外部のプロコーチによる、マネージャー向けの個人セッション体験会を実施する
大切なのは、「教える」ことと「体験する」ことのバランスです。
知識やスキルだけでなく、「コーチングを受ける側の気持ち」を理解してもらうこと。その体験があってこそ、初めてマネージャーたちは部下に対して本物の共感と理解を示せるようになるのだと思います。
Aさんとの出会いは、改めて「体験の力」を実感させてくれました。
どんなに優れた理論も、体験に勝るものはありません。どんなに完璧なマニュアルも、実際の体験には及びません。
マネージャーたちに真の対話力を身につけてもらいたいなら、まず彼ら自身が対話の受け手としての体験を積むこと。それこそが、組織の対話文化を変える第一歩なのかもしれません。