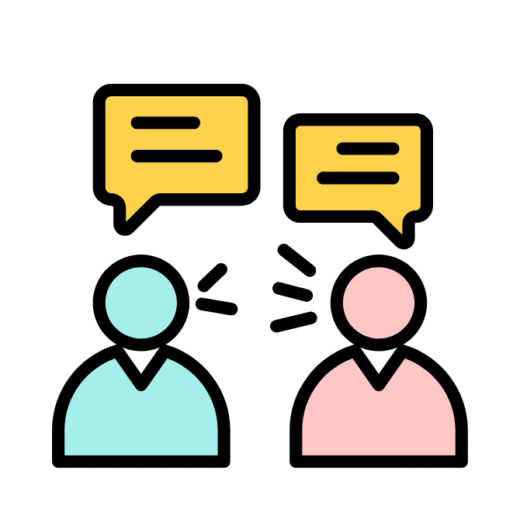
先日、とあるクライアントからこんな相談を受けました。
「私の同僚の〇〇さん、何回言っても分かってくれないし、同じミスを繰り返すんです。どうしたらいいでしょうか…。」
言う方も、言われる方もストレスを感じるばかり…。
読者のみなさまもこんな経験をしたことがありませんか?
「言う側」の気持ちは、みなさんもよく分かると思います。
では、なぜ「言われる側」は変わらず、同じことを繰り返すのでしょうか?
これは「言われる側」の立場になってみると見えてくるものもあります。
ちょっと深掘りしてみましょう。
例えば、みんながいる前で叱られたら、「何もみんながいる前で叱らなくたっていいじゃないか」という思いが湧いてきて、指摘そのものを受け止めることは難しいと感じる人は多いと思います。
では、「1対1」で指摘を受けたらどうでしょう?
これはこれで素直に受け止めることはなかなか難しいものです。
例えば、昔、親御さんから「ちゃんと宿題やりなさい」と言われたことはありませんか?
そう言われて「よし、やろう!」という気持ちにはなれなかったはずです。
仕事についてもそうです。
「目標を達成しなさい」と毎年言われ続ければ、仕事への意欲も減退してしまうでしょう。
人はとかく「他人から強いられること」を嫌います。
自分のことを軽視している人の言うことならなおさらです。
「あの人の言いなりにはなりたくない」という「自尊心」が、心理的な抵抗を生じさせます。
「何回同じことを言っても分からない人、変わらない人」の心理は次のようなものが考えられます。
指摘されることが多いと、都度反論するのも面倒になってきます。
そこで、「はい、分かりました」という常套文句が出てきます。
(ただ、実際には言動は変わりません。)
仮に実行するとしても、「本当はやりたくない」という感情が根っこにあるので、すぐ元に戻ってしまいます。
では、冒頭のクライアントの相談は、「解決できない問題」なのでしょうか?
決してそんなことはありません。
それを解決するのが、筆者(当社)の仕事です。
「何回言っても変わらなかった〇〇さんが、徐々に変わってきた。栄木さん一体何をしたんですか?」
もちろん魔法をかけたわけでも、脅したわけでもでもありません。
それは、いたってシンプルなアプローチです。
それは「対話」です。
特に相手の考えや想いを聴くことを大事にしています。
「なんで対話で変わるの?」
そう思われた読者の方もいるかもしれません。
対話には、相手からの「問いかけ」などを通じて、自身を客観的に振り返る効果があります。
そして、新たな気づきを得ることにもつながります。
「今話していて思ったんですけど…」
「話しているうちに道筋が見えてきました!」
人は、自分で気づいたことの方が行動に起こしやすいものです。
たとえば、他人から「ちゃんと勉強やった方がいいよ」と言われるのと、
「勉強の必要性について自分で気づく」のとでは、その後の行動で雲泥の差が出ます。
「『5分前行動しなさい』と言われるのは縛られる感じがして嫌だった。
でも、話していて『IN TIME』という考えはすごくしっくり来た。」
と言うクライアントもいました。
どちらも「時間内に行動する」という点では変わりません。
ただし、そこに「やらされ感」があるのか、「自発性が伴っているのか」は大きな違いです。
人は、他人からの「説得」よりも、自分の「納得」で自発的に動きます。
なお、対話に臨む姿勢は、なるべく中立的で、ニュートラルな方が良いとされます。
とはいえ、利害関係が強すぎたり、過去に嫌な思いをした、させてしまったなどの「残像」があると、中立的な姿勢で臨むのは難しいものです。
だからこそ、筆者(当社)のような、中立的な第三者が果たすべき役割も大きいと考えます。


