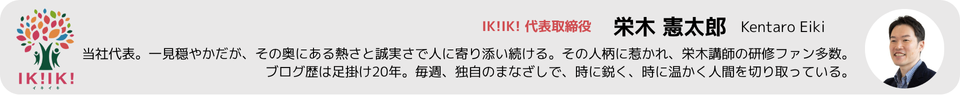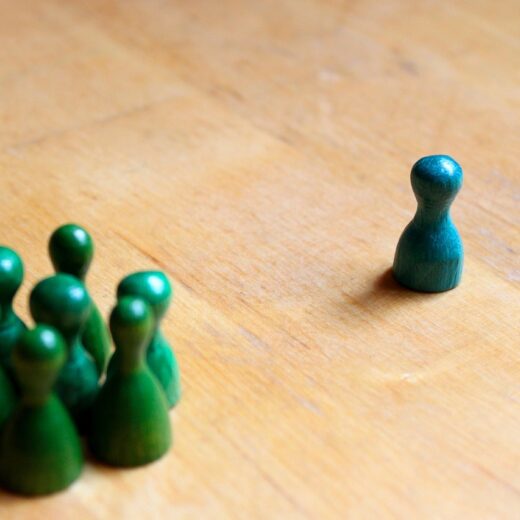
「まだ新人だしな」
誰もが一度は耳にしたことがあるこのフレーズ。
行間を読む文化が強い日本では、この一言が温かい励ましとして機能する場面も少なくありません。
「まだ経験が浅いのだから、焦らずにね」
「失敗しても大丈夫だよ」
そういった優しさや配慮を含んでいることも多いでしょう。
しかし、行間を読み取られない社会、あるいは切り取られて拡散される可能性がある現代においては、この一言がまったく別の意味に変換されるリスクをはらんでいます。
- 「新人だから意見するな」という優位性の押しつけ
- 「あなたはまだ信頼されていない」という暗黙の排他性
- SNSで一部だけ切り取られ、文脈抜きで炎上
では、なぜ同じ言葉でも、ここまで受け止められ方が変わってしまうのでしょうか。
そこで役に立つのが、「優位性」「排他性」「尊重」 の3視点で発言を振り返る方法です。
1. 優位性
相手を下に見ていないか。
「新人だから」という立場を理由に、発言や行動の価値を下げてしまっていないか。
「まだ経験が浅い」という事実を伝えるだけでも、そこに優越感がにじむと受け手は敏感に察知します。
2. 排他性
その価値観を押しつけていないか。
「新人だから黙っておけ」「結果を出すまで意見するな」──こうした含意があると、相手の参加を阻むメッセージになります。
3. 尊重
相手を人として尊重する姿勢があるか。
「新人だしな」でも、「だからサポートするよ」「学べるチャンスだよ」という意図が明確であれば、前向きに届きます。
この3視点は、「新人だしな」だけでなく、職場にあふれる多くのフレーズにも応用できます。
- 「女性だからな」
- 「中途採用だしね」
- 「前例がないからな」
- 「バイトだからな」
言った本人に悪意がなくても、優位性や排他性が含まれ、尊重が欠ければ、それは組織の信頼を削る“弊害”に変わります。
逆に、同じバイアスでも尊重を伴えば、必ずしも弊害になるとは限りません。
バイアスと弊害は別物
多くの人が「バイアス=悪」と捉えがちですが、本質は違います。
人間は誰しもバイアスを持っており、それ自体は自然なこと。
問題は、それが優位性や排他性を帯びてしまうことです。
むしろ、怖いのは「当たり前」になってしまったバイアスです。
たとえば企業をはじめとする経済社会では「結果を出している人が偉い」「利益を上げている人が偉い」という価値観が浸透しています。
これは優位性も排他性も強く、かつ“疑う余地のない常識”として刷り込まれるため、異なる才能や貢献を見えなくしてしまいます。
言葉をやめるのではなく、選び直す
アンコンシャスバイアス研修の現場でよくある誤解が、「この言葉はNG」という“言葉狩り”の発想です。
それでは人は萎縮し、会話は痩せ細ってしまいます。
大事なのは、やめることではなく選び直すこと。
「新人だしな」を「まだ経験が浅いから、今はサポートするよ」に変えるだけで、伝わる印象は大きく変わります。
行間を読む文化が薄れ、切り取り社会が進む現代では、発する側の意図だけに頼るのは危うい時代です。
優位性・排他性・尊重の3視点を持ち、言葉を選び直す習慣を身につけることが、これからの職場コミュニケーションには欠かせないかもしれません。
そして、「新人だしな」と言いたくなったら、ぜひ一呼吸おいて──
「その人が前向きに受け取れる言葉」に置き換えてみてください。
それだけで、チームの空気はきっと変わります。