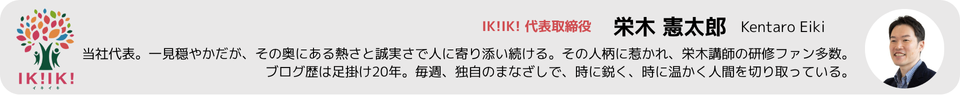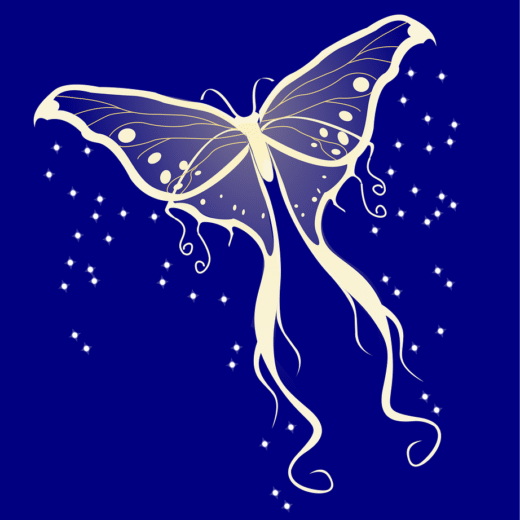
先週、富良野のホテルに泊まった時の出来事です。
露天風呂の入口に一枚の紙が貼られていました。
「蛾が大量発生しています。ご注意ください。」
恐る恐る外に出ると、蛾の気配は無し。安心して温泉に入りました。
ところが、その後、散歩がてら外出すると「大きな蛾」がわんさか街灯の周りを飛び回っていました。
警戒しながら歩いていると、殺虫灯の光に一直線、バタバタと羽音を立て、光に触れた瞬間「バチッ」と小さな火花のような音を残して、蛾が次々と地面にポトリと落ちていくのを目の当たりにしました。
まるで光を追うことが彼らの宿命かのように――。
その光景を眺めながら、ふと「これ、人間も同じじゃないか?」という考えが浮かびました。
人間もまた、「光」に吸い寄せられる存在です。
昔ならダイヤモンドや金、クレオパトラのような“光る存在”。
現代なら、最新の技術、SNS、投資、ポイント、自己成長や美容といった“現代の光”。
どれも私たちの生活を豊かにする一方、その光に夢中になるほど、自分の意思や感覚を見失いがちです。
もちろん、光に惹かれること自体は悪いことではありません。
むしろ、それが人間のエネルギー源でもあります。
ただし問題は「近づき方」。
蛾が光に突っ込みすぎて身を焦がすように、人間も近づきすぎれば燃え尽き、時に身を滅ぼします。
かといって「そんなもの興味ない」と冷め切ってしまえば、好奇心や挑戦心がしぼんでしまう。
熱くなりすぎても、冷めすぎても、どちらにしても“我”を失うのです。
ここでふと気づきました。
蛾(が)と我(が)。
偶然のようで、象徴的な一致。
蛾は光に飛び込み、我は光に吸い寄せられる。
どちらも「強い引力」に支配されています。
ただし、人間には蛾にはない「間(ま)」を置く力があります。
突っ込む前に一瞬立ち止まり、「これ以上近づいて大丈夫か?」と自問することができる。
これこそが“我”をコントロールする知恵であり、人間が持つ特権なのだと思います。
しかし現代は「光」が多すぎるがゆえに、この“間合い”の取り方がかつてないほど難しくなっています。
例えば、こんなことはありませんか?
- SNSやメールの通知が気になって、仕事や勉強の集中力が奪われる
- 「お金・ポイント・投資」という光に過度に執着し、人間関係が後回しになる
- 「効率・タイパ」という光に囚われ、視野が狭まっていく
過剰な光に引っ張られて、夢中になるか、疲れてシャットアウトするか。
どちらかの極端に振れやすい時代です。
だからこそ、自分にとっての「ちょうどいい距離感」を探し続けることが、これまで以上に重要になっているのだと思います。
話は飛びますが、「太陽系」を思い出してみてください。
太陽はまさに「究極の光」。
近すぎれば灼熱、遠すぎれば氷の世界。
地球が生命を宿しているのは、その“ちょうどよい距離”にあるからです。
太陽に「熱烈フォロー」しすぎず、かといって「アンフォロー」もしない絶妙な距離感。
まさに「光と我」の教科書のような配置です。
つまり、光に惹かれること自体は自然。
ただ、「どの距離でその光と付き合うか」を意識的に選べるかどうかが、成熟した生き方の分かれ道になる…。
何事も熱中することは素晴らしいけれど、常に「今、自分は近づきすぎてないか?遠ざかりすぎてないか?」と、小さな温度計を持っておくこと。
それが自分を焦がさずに光をエネルギーに変えるコツだと思います。
蛾たちは本能だけで飛んでいましたが、人間には本能に加えて知恵があります。
本能は私たちを突き動かし、知恵は私たちを守ります。
その両方をバランスよく使うことで、人間はもっと健やかに、そしてしなやかに生きられるはずです。
「自分、今ちょっと蛾っぽくなってないか?」
そう自問することで、心に“間”が生まれます。
・最近、自分が熱くなりすぎているものは何か?
・逆に、冷めすぎてしまっているものは何か?
・その距離感は、ちょうどいいだろうか?
光り輝くものに惹かれる自分を責める必要はありません。
ただ、その距離感をどう保つかを自分で決めることができる――これこそが人間ならではの自由であり責任です。
蛾たちがバチッと散っていく姿は、その当たり前のようでいて大切なことを、あらためて教えてくれました。
蛾に学び、我を知れ。
光に吸い寄せられることは悪ではなく本能。
けれども、どこで止まり、どこで引き返すかは知恵。
みなさまにとっての“光との距離”はどのくらいでしょうか?