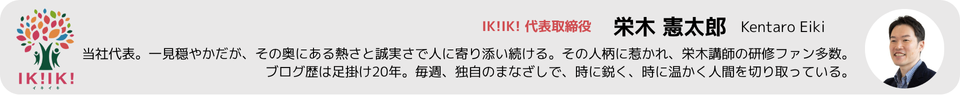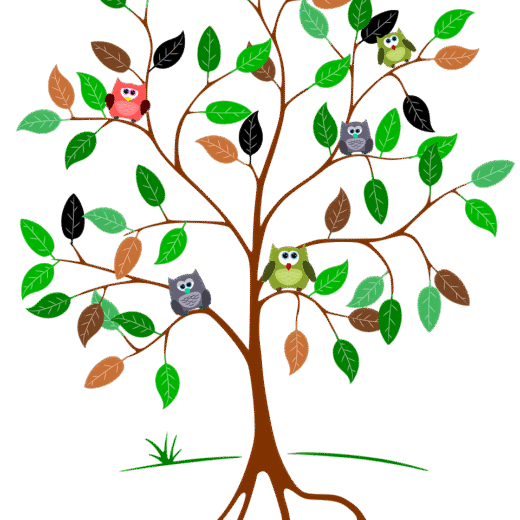
最近、いろんな会社で“パーパス経営”という言葉を耳にします。
理念や存在意義「何のために働くか」を定め、全社員が同じベクトルで動く。
とても大事なことです。
でも筆者は、どこか引っかかるものを感じています。
多くの企業が、理念やパーパスを「上から下へ」落とし込もうとしています。
つまり、“理念をどう行動に変換するか”という発想になっているのです。
たとえば、「金融を通じて地域社会に貢献する」という企業パーパス(存在目的)があるとします。
そのパーパスを社員の行動に落とし込むために、こんな問いが投げかけられます。
「では、あなた個人として何をしますか?(個人パーパス)」
「どんな行動を取れば“地域社会への貢献”につながりますか?」
もちろん、考えること自体は悪くありません。
でも、筆者はそこに“違和感”を覚えます。
なぜなら、それは理念をTodoリストに変えてしまうからです。
例えば、「地域イベントに参加する」「CSR活動を増やす」といったように。
「貢献」といった言葉を、“やること”にしてしまった瞬間、その言葉は魂を失います。
さらには、現場からはこんな声も漏れてきます。
「これ書いたところで、結局、評価されるのって業績だよね」
「正直、忙しくてそんなこと考える余裕がないよ」
「理念とかの前に、まず人を増やしてほしい…」
話は変わりますが、明治大学ラグビー部には「前へ」という有名なチーム理念があります。
一見シンプルですが、これはただのスローガンではありません。
監督が「前へ行け」と命じるから前に出るのではなく、
その言葉が血肉になっているから、自然と前に出る。
でももし、この「前へ」をTodoに落とし込もうとしたらどうなるでしょう。
「タックルでは一歩前に踏み込む」
「前向きに物事を捉える」
「一歩でも多く足を掻く」
……たちまち“行動マニュアル”になってしまいます。
「前へ」は、行動を指示する言葉ではなく、
自分の中から湧き出る力そのものです。
企業のパーパスも同じです。
本来は、社員一人ひとりの中に根を張り、
自分なりの形で表現されるものです。
でも、「落とし込む」「浸透させる」といった発想で取り扱われると、
パーパスは“義務”になってしまいます。
言葉としては立派でも、心には響きません。
筆者は思います。
理念やパーパスは、上から浸透させるものではなく、下からにじみ出るものだと。
会社という「樹木」でいえば、理念やパーパスは“根っこ”のような存在です。
根がしっかりしていれば、枝は自由に伸びる。
太陽に向かう枝もあれば、影をつくる枝もある。
でも、どの枝も同じ根でつながっている。
やり方は人それぞれでいい。
でも、想いは一つ。根っこではしっかりつながっています。
では、どうすれば“根っこ(理念やパーパス)でつながる組織”をつくれるのでしょうか。
筆者は、3つのことが大切だと思っています。
① 言葉で合わせず、体験でつながる
理念はスローガンではなく、体験の中で生きるもの。
現場での成功体験や苦労を共有する中で、自然と“共通の価値観”が育ちます。
理念は唱えるものではなく、“思い出されるもの”です。
② 「浸透」ではなく、「共鳴」
浸透という言葉には、“上から下へ”という構造が含まれています。
でも理念は、“響き合う”もの。
教えるのではなく、問いかける。
「あなたが“地域社会に貢献できたな”って思ったのはどんな瞬間だった?」
そんな対話の中で、理念は血の通った言葉になります。
③ 行動を縛らず、想いを広げる
理念を行動規範にしてしまうと、人は「正解探し」を始めます。
一種の”教義”のようになって、思想統制にもつながりかねません。
でも、理念とは正解ではなく、“原点”です。
人が迷ったときに立ち返る場所。
その“想いの原点”があるからこそ、「自由」が機能し、創造性や主体性が発揮されます。
枝葉をそろえるより、根っこをそろえる。
やり方を教えるより、想いを共有する。
Todoに落とし込んだ瞬間、理念は命を失う。
でも、体験と共感を通して“血肉”になった瞬間、
理念は生きはじめます。
やり方は違っていい。
でも、根っこは一緒。
理念とは、“伝えるもの”ではなく、“宿すもの”。
そのとき、組織ははじめて——前へ進む力を手に入れるのではないでしょうか。