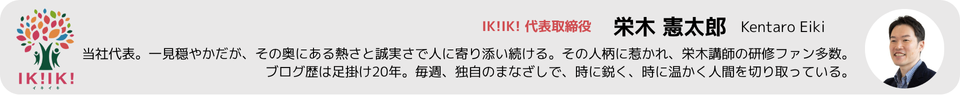最近、思うことがあります。
私たちは、いつの間にか“外の世界”に心を奪われる時間が増えているように感じます。
画面を開けば、誰かの発言、ニュース、SNSのコメントが目に飛び込んできます。
「誰それが炎上した」「あの人の態度が気になる」「上司の言い方が腹立つ」……。
気がつくと、私たちの思考は四六時中“他人”や“出来事”に反応し続けています。
こうして外に意識が向いているとき、心の中では何が起きているのでしょうか。
多くの場合、違和感やモヤモヤ、イライラ、不安、焦りといった感情が湧き上がります。
その原因を、「あの人が悪い」「環境が悪い」と外に結びつけた瞬間、私たちは“他責”の状態になります。
筆者自身も例外ではありません。
現代の環境に染まっていると、ネガティブな感情が湧き起こったとき、
その矛先を「そのような思いにさせた他者」に向けてしまうことがあります。
そして、他責の感情に覆われて思考を堂々巡りさせたあとで、
「あ、いけない!」と、ふと我に返ることがあります。
その瞬間に気づくのです。
感情の裏には、必ず自分の中の価値観やこだわりがあるということに。
「こうあるべき」「わかってもらいたい」「認められたい」——
それらが刺激されたとき、人は感情的に反応してしまうのです。
大切なのは、感情が動いた瞬間に「なぜ自分はこう感じたのか?」と一歩立ち止まることです。
それが“自責”ではなく、“自省”の姿勢です。
「自省」とは、自分を責めることではなく、自分を理解することだと思います。
自分の”思考のアルゴリズム”を少しずつ観察していくうちに、
「なるほど、自分はこういうときに焦るんだな」
「こういう言葉に反応しやすいんだな」
と気づけるようになります。
そうすると、他人の言動に振り回されることが減り、少しずつ心が自由になっていきます。
今の社会は、外に反応するしくみに満ちています。
①「感情の強さ」が可視化されるSNS構造
SNSは“感情の強さ”を報酬に変えるように設計されています。
たとえば、怒りや共感といった強い感情を込めた投稿ほど「いいね」やコメントが集まりやすく、
アルゴリズムはその投稿をより多くの人に拡散します。
結果的に、穏やかな言葉よりも刺激的な表現が目立つ世界になります。
私たちは気づかないうちに、“心が動くものほど評価される”空間の中で生きているのです。
それが、反応的な思考を日常的に強化しています。
②視覚情報の洪水と、失われた余白
さらに、視覚から得る情報量が圧倒的に増えたことも大きな要因です。
たとえば20年前、私たちが1日に目にしていた広告や映像はせいぜい数百件程度だったそうです。
今は、SNSのタイムライン、動画配信、デジタルサイネージ、ニュースアプリなどを通して、
数千単位の“刺激”が毎日、視覚を通して流れ込んでいます。
電車に乗っていても、つり革の上のモニターに目を奪われ、
信号待ちのわずかな時間にもスマホを開いてしまう。
意識していなくても、外部の情報は常に私たちの脳を刺激しています。
その結果、脳は外の処理でフル稼働し、
“自分の内側を見つめる余白”を失っているのです。
③「流し読み社会」がつくる反応的思考
そしてもう一つ、一つの情報を深く考えなくなったことも無関係ではありません。
スクロールすれば次々と情報が出てくる環境では、
一つの記事をじっくり読むよりも、“流し読み”が習慣化していきます。
すると、一つの出来事を深掘りする前に、
次の刺激が上書きされていく。
忘れるスピードが速くなり、
思考はどんどん浅く、反応的になっていくのです。
だからこそ、筆者は思います。
現代において最も贅沢な時間とは、
「自分と静かに向き合う時間」ではないかと。
それが、「自分を知ること」につながります。
そして、自分を知ることが「自己の内的成長」のベースになります。
IK!IK!が行っている活動の本質も、まさにそこにあります。
私たちは、日々の忙しさの中でつい後回しにしがちな“内省の時間”を意図的につくり、
自分を理解するための「技法」を伝えています。
それは、他人を変えるためではなく、
自分をより深く理解し、よりよく生きるための時間です。
外の世界がどれだけ騒がしくても、
自分の中に静けさを取り戻せる人は、
周りに流されずに、やさしく、しなやかに生きていける。
筆者はそう信じています。