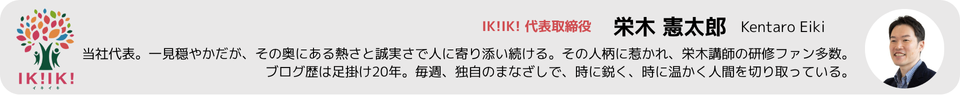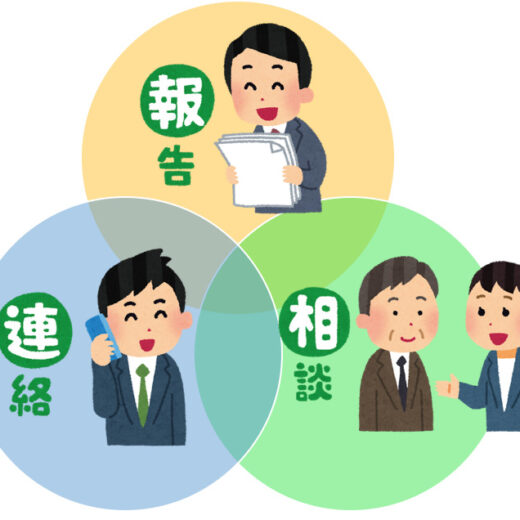
先日、ある企業の担当者から相談を受けました。
「最近の若手が、報連相できなくて困っています。
研修で“ちゃんと報連相しよう”と伝えてほしいんです。」
その言葉を聞いた瞬間、筆者はふと考えました。
——本当に“若手だけ”の問題なのだろうか?
■ 若手だけでなく、自分も、そして社会全体の“血流”が滞っている
思い返すと、筆者自身にもこんなことが増えています。
・メールを返そうと思いながら、後回しをしてつい忘れてしまう
・既読をつけたけれど、返信のきっかけを失う
・電話すればいいと分かっていても、相手の都合が気になりためらう
これは若手に限らず、多くのビジネスパーソンに起きている現象です。
いま、 社会全体が“報連相の血流不足”に陥っています。
■ 報連相は組織の生命線──まさに“血流”
よくよく考えると、報連相ができているかどうかは
組織が健全に機能しているかの“生命線”そのものです。
血液が身体のすみずみまで酸素を運ぶように、
報連相は、情報・意図・違和感 を届けます。
誰かひとりが報連相を止めれば、そこに“小さな血栓”ができます。
- 返信の遅れで誤解が生まれる
- 共有漏れでトラブルの再発防止が遅れる
これは日常に潜む血栓です。
そして、大きな組織ほど“見えないところで”血栓が生まれやすい。
長年、現場の声が届かず、意図がねじれ、問題が見過ごされる——
そんな不祥事は、どれも根っこは同じです。
報連相が止まれば、組織のどこかに必ず血栓ができます
■報連相が難しくなった最大要因は“情報過多”
ではなぜ、こんなにも報連相が難しくなったのか?
理由のひとつは、
情報量が“増えすぎた” ことです。
Slack、Teams、メール、LINE、チャット…
常に大量の情報(=血液)が流れ続けることで、
・小さな共有がすぐ埋もれる
・重要な連絡が行方不明になる
・「あとで返そう」が本当に“あとで”になる
つまり、情報過多が“小さな血栓”をつくり、血流の目詰まりを起こしています。
流れは速いのに、詰まりやすい。
これが現代組織の“血流障害”です。
■ 若手に増えている“チンゲンサイ”と“コマツナ”
この血流障害は、若手の行動にも表れています。
● チンゲンサイ
- (ちん)沈黙して
- (げん)限界まで言わず
- (さい)最後までやり過ごす
しなしなになるまで抱え込むタイプ。
● コマツナ
- (こま)困ったら
- (つ)使える人に
- (な)投げる
とりあえず鍋にポンと入れてしまうように、すぐ誰かに丸投げするタイプ。
どちらも責めるべきではありません。
血流が悪い環境では、誰もが自然とそうなる傾向にあります。
■だから、報連相ができる人は“希少スキル”になっている
こうしてみると、報連相が“当たり前”だった時代は終わったと言えます。
情報のノイズが多すぎる今、
必要な情報を、必要な人に、必要なタイミングで届けられる人は極めて希少です。
さらにこの能力は、
AIがもっとも代替しづらい“人間らしさ”そのものです。
だからこそ、AI時代に価値が上がるのは、報連相の質をコントロールできる人と言えそうです。
■ 上司側の“おひたし”こそ、血管をしなやかにする
そして、報連相をする側だけでなく、
受け取る側の姿勢も血流を決める要因です。
● おひたし
- (お)怒らず
- (ひ)否定せず
- (た)助けて
- (し)指示する
これは、 詰まりがちな血管をしなやかに保つ“上司の技”です。
おひたしができる上司も希少です。
だからこそ栄養価も高い。
■ 最後に──新語“さつまいも”を贈ります
せっかくなので、新語を作ってみました。
(芋好きの妻が発明しました…)
「さつまいも」
- (さ)さっさと
- (つ)つたえる
- (ま)まよったら
- (い)いう
- (も)もっと聞く
明日からはぜひ、 “さつまいも”
を合言葉にしてみてはいかがでしょうか。。
血流がよければ、冷え性にもならず、組織もホクホク温まりやすくなります。
そして、そこには人がイキイキと働く未来が待っています。