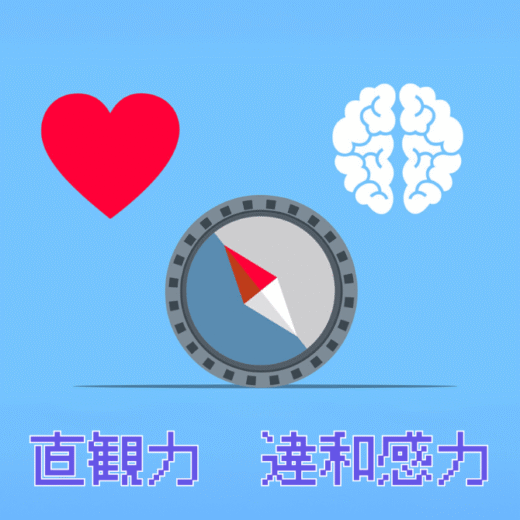
「あ、これなんとなく行けそうかも」という直感。
「あれ、これなんか変だぞ?」という違和感。
人間である以上、誰しもこのような直感や違和感を抱くことはあります。
では、「自身の直感や違和感に従って行動できているか?」と言われると、その答えは分かれてくると思います。
現代社会は情報過多で、あらゆる方向から「こうすべきだ」「これが正解だ」といった声が飛び交っています。
AIの予測やデータ分析も便利ですが、それに頼りすぎると、どこか「自分の感覚」が置き去りにされてしまうような気がします。
このように、自分の心から湧き起こる声を遮(さえぎ)るのは「常識」や「誰かの意見や忠告」であったりします。
「自分だけがそうする」ことへの不安、「みんながそうしていること」への安心感…。
つまり、自分の立場や身を守りたいという「自己防衛本能」が、自身の直感や違和感を覆いかぶせます。
しかしこれは同時に、自分の直感に従って行動する中で磨かれる「直感力」、
違和感に耳を傾けて行動することで磨かれる「違和感力」を鈍らせることにもつながります。
すると、ますます何かを決断する際に、自分以外の第三者に委ねてしまうことにもつながります。
それが結果として、ますます他者依存の生き方を強化していきます。
これが精神の不安定さにもつながっていきます。
そういった意味では、直感力と違和感力を磨き、それらに従って行動を起こしていくことが、これからの時代の「自己防衛」につながると筆者は強く思います。
それは、単に成功への道筋を見つけるためだけではなく、迷いや不安の多い時代に「自分軸」を持つための重要な手段だと思います。
例えば、ビジネスや人間関係で、「(みんなはこう言っているけど)なんか引っかかる」「この方向性、ちょっと違う気がする」といった感覚が、失敗を未然に防いでくれることにつながります。
それだけではなく、この感覚が磨かれていると、自分にとって「これは間違いない」と感じた方向性に迷わず進めるようになります。
迷いの少ない意思決定ができるというのは、これからの不確実な時代において、大きな強みになるはずです。
とはいえ、この感覚が磨かれてないと、バイアスがかかった独り善がりな判断となって、大きな失敗を招くこともあります。
では、具体的にどうしたら直感力と違和感力は磨かれるのでしょうか?
「違和感力」を磨くためには、まず日常の小さな違和感を見逃さないことが大事に思います。
「なんかこの乗客の様子、ヘンだぞ」と感じたら、それをただ放置せず、「声をかけてみる」など実行に移してみます。
「小さな違和感➡察知➡ちょっとした勇気➡行動」の繰り返しによって、この感性は磨かれていきます。
反対に、違和感を感じても考えすぎて行動に移せなかったり、「みんなやっていないし」と思って、見て見ぬフリをすると感覚は鈍っていきます。
このように、小さな違和感に丁寧に向き合う習慣が、大きな違和感に対する感度を高めてくれます。
一方で、「直感力」は経験や知識の蓄積から生まれることが多いので、自分が関わる分野での「現場経験(=一次情報)」を増やすことが直感力の向上につながると思います。
現場で五感をフルに活用することで、第六感(Six Sense)への接続を図っていきます。
さらに、常識に縛られない「遊び心」もあるとなお良いかもしれません。
日常の中にちょっとした変化を取り入れるだけでも、感覚が研ぎ澄まされます。
例えば、普段とは違う店でランチをとったり、意識的に初対面の人と話す機会を作ったりする。
こうした「日常に違う刺激を加える」ことが、直感力をより高めてくれます。
もちろん、直感や違和感だけを頼りにすべてを決めるわけではありません。
ときにはデータや他人の意見を参考にすることも必要です。
ただ、最後に決めるのはやっぱり自分。
そして、その「自分の感覚」に自信を持てるかどうかが、「正解」のないこれからの時代を生き抜く力につながると信じています。


