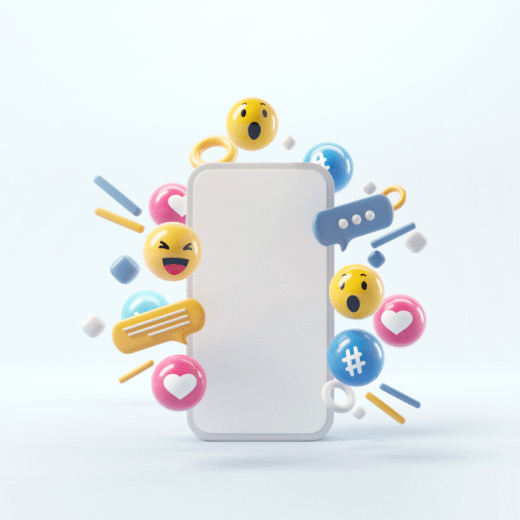
先週話題にした兵庫県知事選、いまだに熱気冷めやらぬ様子です。
今度は、SNS戦略と公職選挙法が取り沙汰されています。
実は、筆者自身はInstagramもX(旧Twitter)もTikTokやっていません。
ですので、SNSの「拡散」や「炎上」という感覚がいまいちピンとこない部分もあります。
それでも、今の時代、SNSが認知を広げるための強力なツールだということは重々承知しています。
ですが、その「威力」が増せば増すほど「副作用」も大きくなります。
今回のケースで目立ったのは、「SNSが怨嗟(えんさ)感情を引き起こしやすい」という点です。
#怨嗟…恨みや嫉妬のような負の感情。
これは厄介なもので、目には見えませんが、あるきっかけで一気に表に出てきます。
たとえば、SNSで他人の華やかな生活や成功談を見て、「自分は恵まれていない」と思い込んでしまうことはありませんか?
そうなると、時に怒りや嫉妬心が膨れ上がり、投稿者に向けた攻撃的なコメントや、さらには炎上に発展することもあります。
SNSの「認知向上」というポジティブな側面だけを見て、その投稿が他者にどう響くか、つまり「副作用」を軽視してしまうと、今回のような事態が起こり得ます。
今回やり玉に挙げられている女性のSNS投稿を見てみましたが、どうも「受け手の感情」に配慮が足りなかった印象です。
結果として、SNSで成果を出しつつも、自らそのSNSで失敗を招いてしまった…なんとも皮肉な話です。
さて、この女性の母校である慶應義塾大学の創設者、福沢諭吉。
彼の思想が現代のSNS時代にも意外なほど通じるので、以下の通り共有いたします。
福沢諭吉が活躍した文明開化の時代、海外からの膨大な情報が日本に押し寄せました。
これは、現代の情報化社会とよく似ています。
当時も今も、情報の氾濫によって「他人との比較」が一層強調され、不満が増幅される傾向があるのです。
そして、現代ではSNSのアルゴリズムがこれをさらに悪化させています。
SNSはユーザーの興味に合わせた投稿を次々に見せてくれる仕組みですが、それが時として偏見や感情を強化する温床になることもあります。
福沢諭吉が『学問のすすめ』で説いた「批判的思考」が、いまなお重要だと感じるのはこういう理由です。
自分に入ってくる情報をただ鵜呑みにせず、取捨選択し、自分なりに考える力が求められるのです。
でも、それが十分でないと、流れ込んでくる情報に感情が振り回され、不満がどんどん膨れ上がる…。
SNS時代の「副作用」はまさにここにあるのだと思います。
では、私たちはこの時代にどう立ち向かえばいいのでしょう?
ここでまた福沢諭吉の教えが参考になります。
彼は「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず(他人と比べるのではなく、自分の努力で価値を見つけるべき)」と説きました。この考え方は、SNS時代においても怨嗟感情を和らげる鍵になるのではないでしょうか。
さらに、福沢諭吉は個人の成功が社会全体の発展と調和すべきだとも考えていました。
現代の情報社会でも、「自分さえよければいい」という視点ではなく、社会全体の利益を考える視点、つまり「公共心」が求められているのではないでしょうか。
SNSは便利なツールですが、その影響力はとても大きいです。
だからこそ、投稿する際には「この投稿が誰かの感情にどんな影響を与えるだろう?」と意識することがより重要になってきます。
筆者自身、このコラムを通じて、読者の皆さまが前向きな気づきを得られるよう意識しています。
これからも、感情に寄り添いながら、少しでもポジティブな社会をつくる一助となるような文章をお届けしたいと思います。


