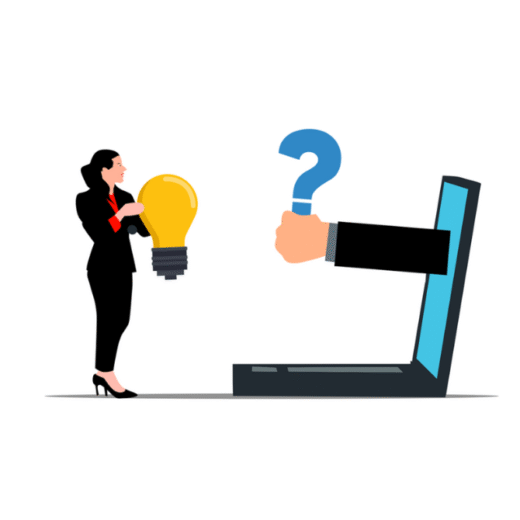
先週、筆者が新入社員時代に5年間過ごした第二の故郷「新潟」にて、研修を行ってきました。
テーマは「コミュニケーション」と「人材育成」。
今回も、筆者の“失敗事例”や“しくじり体験”を交えながら、受講者の皆さんと深く考える時間を持ちました。
研修中にこんな質問をいただきました。
「コンサルの先生でも、コミュニケーションや人材育成に苦労しているなら、私たちにはもっと難しいのでは?」
確かに、講師として「方法論」はお伝えしますが、「こうすれば必ずうまくいく」という万能な解決策は、人間関係や人材育成には存在しないと思っています。
(反対に、それを喧伝している会社や人がいたら、筆者は全力で疑います…)
人間関係構築力や人材育成力は、リアルな関係性の中でこそ育まれていきます。
座学で学ぶスキルやテクニックは、あくまで「道具」に過ぎません。
例えば、筆者自身もチーム活動を行いながら、日々「つまずき」を経験しています。
しかし、その過程で「大切な何か」を学び取り続けています。
そして、その学びに終わりはないと感じています。
人間関係や人材育成がうまくいかないとき、多くの人は次のような感情を抱きがちです。
「なぜあの人は分かってくれないのか?」
「これだけ手塩に掛けて育てていたのに、なぜ辞めてしまうのか?」
時にはそれが「裏切り」や「憎しみ」に変わることもあります。
しかし、このような「他人を主語」にした捉え方では根本的な解決にはたどり着けません。
かといって、自分を責める必要もありません。
大切なのは 「今、自分は何を問われているのか?」 を自問することです。
過去に原因を求めるのではなく、未来の「ありたい姿」を軸に考えることが大切です。
「この状況は、自分をどう成長させようとしているのか?」と問いかけるのです。
この姿勢を持つことで、心理的な葛藤を乗り越えながら「心の器」を広げることができます。
そして、この「器量」が結果的に人間関係や人材育成をより良い方向に導くと実感しています。
今回の研修でこの話を共有したところ、受講者の方々も深く納得された様子でした。
筆者が「コンサル」と呼ばれることに抵抗を感じる理由はここにあります。
スキルや理論だけで解決できる領域もありますが、人間関係や人材育成に関しては通用しない部分が多いからです。
なぜなら、扱うのは「人の心」だからです。
筆者自身も、日々「人としてのあり方」を問われながら過ごしています。
この経験を通じて、「悩む」ことそのものが成長への糧であり、人間関係や人材育成の本質であると改めて感じています。


