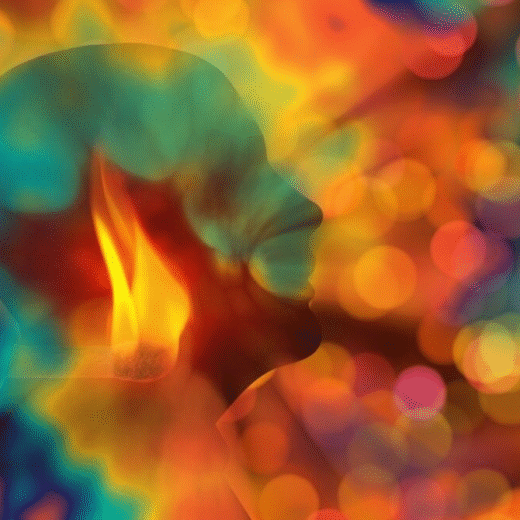
今年度は、当社IK!IK!のテーマとして「ギラギラ」を掲げました。
顧客の成果に「ギラギラ」する。
自身の成果に「ギラギラ」する。
そんな意気込みで、仲間とともに2か月間駆け抜けてきました。
おかげさまで業績は順調に推移し、世の中に貢献できている実感もあります。
これは大変有難いことなのですが、一方で、筆者自身「息切れ」を起こしてしまったようです。
先週は、何をするにも意欲的になれず、やや燃え尽き症候群(バーンアウト)になっていました。
例えるならば、仕事は「長距離走」のようなものなのに、この2か月は「100m走」のごとく全力疾走をしてしまった感じです。
何かをするにつけ、「~しなければ」という義務感や、「~しよう」という意識が入り込んでいました。
それでも最初は気合いと根性で乗り切っていましたが、さすがに先週は何かをすることが億劫(おっくう)になる感覚に陥り、仕事が手につきませんでした。
何かをしようと意識すればするほど、それと同じくらいの力で現実から逃れたくなる…という感覚です。
仕事がはかどらない一方で、疲労感だけが蓄積していきました。
そんなとき、手に取った一冊の本の一節が、筆者の心に沁み入ってきました。
それは以下の通りです。
――
「~しよう」とする意識がある限り、力みは体からなくならない。
意識でコントロールする習慣を捨てる。
「~しよう」という意識を止める。
それがうまくできたときに、はじめて力は抜ける。
がんばろうとすれば、「~しよう」と強く思って行動することになる。
すると力が入ったドタバタした動きになり、流れるようにものごとを進めることができなくなる。
その結果、的を外してしまうことは少なくない。
仕事でも普段の生活でも、あるいは人間関係においても、「力を抜く」ということはとても大切なことだ。
(中略)
力を抜くとは、「押してダメなら引いてみよ」というときの「引く」とはまた違う。
力を全身から抜くと、力はゼロになるのではなく、核分裂反応を起こすようなエネルギーがそこから湧いてくる。
脱力した体はただの無力な状態にあるが、力が本当に抜かれた体はどこにも一切の緊張(こわばり)がなく、弾力を持ったボールのように柔らかい状態にある。
(中略)
力みをなくすと本当のしなやかな強さが生まれるということを、体を引き合いにして説明したが、このことは単に動作にとどまるものではない。
力を抜くことの重要性は、仕事や日常においても言えることだ。
―――
「いいものを作らなければ」「もっと貢献しなければ」「責任感を持って行動しなければ」…
筆者の中から様々な「~しよう」「~しなければ」という力みが抜けました。
もちろん、これらを放棄することとは違います。
いいものを作る、顧客に貢献する、責任感を持って行動することに変わりはありません。
ただ、そこに力みが抜けただけです。
効果はてきめんでした。
力みが抜けてから、あまり意識せずとも物事に取り組めるようになり、結果として仕事のパフォーマンスは高まりました。
しかも「疲れ知らず」という「特典」までついてきました。
「まだまだやれる」という感覚です。
筆者なりの体験で感じたことを言葉で適切に表現するのは難しいですが、「しようと思わずに、する」感覚です。
例えるならば、起床時に、「起きよう」「起きなければ」と思わずに、スッと起きる。
整理整頓も「片付けなくちゃ」と思わずに、スッと片付ける。
仕事も「〇〇を仕上げなきゃ」「〇〇を仕上げよう」と思わずに、ただ取り組む。
そんな感覚です。
それは、ただひたすら座禅に取り組む「只管打坐(しかんたざ)」という言葉の意味合いにも近いかもしれません。
座禅においては、そうすることで「心身一如(しんしんいちにょ)」=「体と心が一つになる」と言われています。
人間である以上、不安、願望や欲求などの感情はなくなりません。
しかし、これらを強く持ちすぎると「~しよう」「~せねば」という力みが入ってきます。
それが、「焦り」「気負い」や「疲労感」などの形となって現れて、自らを苦しめる原因となります。
特に現代社会は、様々な情報が入ってくるのでそのような「意識」が入りやすい環境とも言えます。
ですので、力みを自覚したら、少し抜いていく感覚を持つのがちょうど良いのかも…と感じた今日この頃です。


