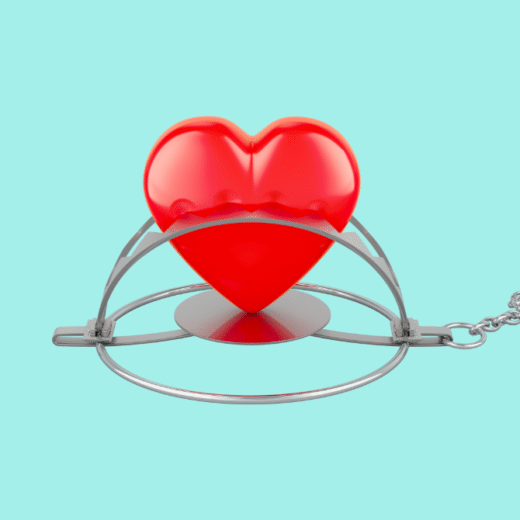
筆者が学生の頃、2つのコンビニエンスストアでアルバイトを経験しました。
高校時代は、ローソン。
大学時代は、セブンイレブン。
(※前提として、コンビニエンスストアはオーナーの方針が色濃く打ち出されます。ですので、同じチェーン店でも店舗によって方針の濃淡は異なります。)
今思えば、筆者が勤めていたローソンはとても店員に優しかったです。
「夏の日の1993」が店内で流れている頃です。
今では考えられませんが、給料を前払いにしてもらったり、陳列期限切れの弁当やデザートを持ち帰ることができたり、早朝からシフトに入ると時給は900円と、当時では高めでした。
かなり居心地が良かったのを覚えています。
ただ、お客様へのサービスはと言うと、それはお粗末でした。
お客様で長蛇の列ができたとしても、そんなのはお構いなしに片方のレジを閉めて、1つのレジで店員2人で喋りながら対応することはざらでした。
陳列も乱れ、制服の着こなしも乱れ…、かなり風紀が乱れていたように思います。
それでも、オーナーからはお咎めなし。
言うなれば、「ぬるま湯職場」です。
それでも、高校生の筆者にとっては、都合のいい場所でした。
一方で、大学時代3年半勤めたセブンイレブンは、オーナーの方針が厳格でした。
陳列期限切れの商品と言えど、一切持ち帰ってはいけません。(それが当たり前ですが…)
アルバイト1人に対する役割が時間単位でぎギッシリ埋まっていて、テキパキこなすことが求められます。
オーナーの指導は厳しく、事細かく注意されることがよくありました。
(反抗するようなものなら、烈火のごとく怒られることも…。)
また、アルバイトがサボってないか、時折見回りに来ることも…。
オーナーがいつやって来るかわからない恐怖(?)におののきながら、3年半過ごしました。
言うなれば、「ギスギス職場」です。
あれから30年近く経ちましたが、
高校の頃勤めていたローソンは閉店しています。
一方、大学時代勤めていたセブンイレブンは今も商売繁盛です。
また、大学時代のセブンイレブンでの経験は「仕事の土台」となり、今の自分の仕事に生かされています。
高校と大学のアルバイト経験だけで、当然すべてを語れるわけではありませんが、
仕事は、対価を得る以上「厳しい要求」はつきものです。
要求レベルが上がっている現代社会はなおさらです。
ですので、筆者も経営者の立場として、メンバーには「プロとしての自覚やこだわり」を持ってほしいのが正直なところです。
とはいえ、厳しさを全面に出すわけにはいかないのが、今のご時世の難しさです。
以前、メンバーの仕事の対応にどうしても納得が行かず、「ネガティブフィードバック」をすることがありました。
すると、メンバーから「それは決めつけではないか」とか「感情的になる人とは仕事はしたくない」と言われ、「栄木さんとは一緒に仕事ができない」と辞められてしまった“しくじり体験”があります。
こんなご時世ですので、筆者も言い方にはかなり気を遣いましたし、
メンバーに思うところはあっても、あえてそれを呑み込むことはよくありました。
メンバーとして迎え入れたからには、気持ちよく仕事をしてもらいたかったからです。
「本当は言いたいのに、言えない」
メンバーに「厳しい要求」ができず、「いい人」になってしまう自分。
それが結果として、メンバーの「仕事の質」がなかなか上がらない理由の一つになっていました。
筆者のメンバーへの接し方は、冒頭の「ローソンのオーナー」のそれに近いのかもしれません。
ただ、それで困るのは「お客様」です。
メンバーから「いいね!」「やればできる!」「それでいいよ」と褒められても、お客様はシビアに「結果(アウトプット)」で判断します。
ですから、「お客様の期待に応える」という点では、セブンイレブンのオーナーの接し方に分がありそうです。
とはいえ、当時のオーナーの関わり方は、今だったら「アウト」かもしれません…。
筆者だけではなく、このジレンマに悩んでいる管理職や指導者は多いと思います。
これが、いわゆる「心理的安全性の罠」です。
この罠にハマってしまうと、仕事の成果に負の影響を与えてしまいます。
では筆者は、もう誰にも厳しいフィードバックをしていないのか…というと、そんなことはありません。
筆者自身、「顧客への貢献」ということに関しては、厳しい基準を持っている方だと思います。
ですから、言うべきときは言いますし、逆に筆者が顧客の期待に沿っていないようであれば「率直に言ってほしい」という思いはあります。
ありがたいことに、成果に向けて、「ズケズケ言い合える」メンバーがいるのも事実です。
そして、これこそが「心理的安全性」の本当の意味合いになります。
「成果に向けて、お互いにダメ出しをしても、それで関係性が崩れる事は無い。」
それが、改善・修正による「質」の向上を生み、成果にもつながります。
では、「真の心理的安全性」を醸成していくためにはどうしたらいいのでしょうか?
一人ひとりが、「伝え手」として伝え方に配慮することや相手を尊重する姿勢はもちろん大事です。
ただ、実はもう一つ大切なことがあります。
それは、「受け手」の度量を広げていくことと筆者は考えます。
厳しいフィードバックを受け入れる「勇気」とも言えます。
もちろん、単なる批判に終わったり、誹謗中傷になることは良くないです。
一方で、「仕事で本当に大事なこと」を伝えるための耳に痛いフィードバックは成長の肥やしになります。
「受け手」がその違いに気づけるかどうかが大事です。
VUCA(不確実であいまいな)時代と言われる現代において、仕事の難易度はますます上がってきます。
だからこそ、成果を出すためにも「心理的安全性の罠」に陥らず、「真の心理的安全性」を一人ひとりが育んでいくことが大事になってきくると筆者は考えます。
※長文、ご容赦ください…。


