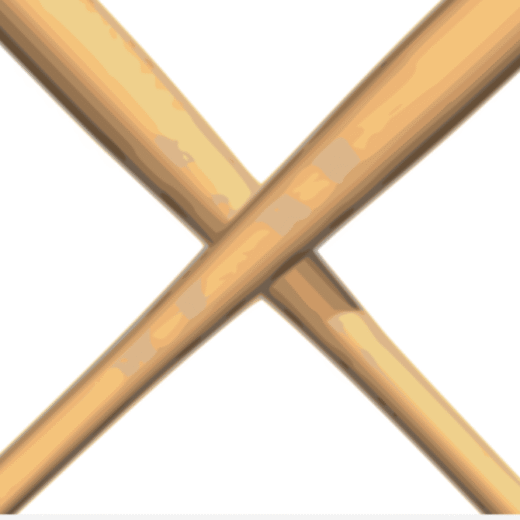
夏の甲子園、慶応高校の優勝は話題を呼びました。
大会前、「今年の優勝校はどこだと思う?」と聞かれた際に、筆者は「慶応高校」と答えていました。
別に予言者だとか言いたいわけではなく、慶応高校は「成果」を出すための理に適った取り組みをしていると思ったからです。
優勝しその取り組みが知られることによって、高校野球も「新時代」に向かっていく…そんなストーリーを思い描いていました。
(ちなみに応援していたチームは、土浦日大高校です)
慶応高校野球部の取り組みは、筆者も以前から知っていました。
わかりやすく言うと、以下の通りです。
・レギュラー・控えメンバー関係なく、一人ひとりがチームメートとして尊重されている
・ワイガヤ・選手同士の話し合いを大事にしている(自主性の尊重)
・多くの学生コーチが存在し、部員が自分の考えを話せる機会を持てている(対話重視)
坊主頭にするかしないかも、選手同士の話し合いによるの自己決定に委ねたわけです。
もちろんこれだけで成果が出るわけではありません。
場合によっては、馴れ合いだけの「ぬるま湯」組織になることもあります。
そこで大事になってくるのが、
・自己規律
・他者への思いやり
です
誰かに言われなくても、また、ルールで決まっていなくても、自分のモラル(良識・規律)に従って行動することです。
他者からの制約が少ないからこそ、「自分の判断基準」に磨きをかけていくことが大事になってきます。
そして最も大事なのが、「何のために?」という目的です。
ここがブレてしまうと、チームがあらぬ方向に向かってしまいます。
高校野球を通じて、
・困難を乗り越えた先の成長を経験する。
・自分自身で考えることの楽しさを知る
・スポーツマンシップを身に付ける。
この3点こそが高校野球が持つ価値の本質だと、慶応高校・森林監督は言っています。
もちろん、競技において「勝つこと」は大切です。
ですが、「勝つことがすべて」ではありません。
「何のために勝つのか?」を考えることが、何よりも大切です。
「慶応高校が優勝することで『高校野球にとって本当に大事なものは何か?』を世に訴えかけること」は、森林監督にとって、大きなモチベーションになったと推察します。
こうなってくると、勝つための戦略・戦術だけに囚われず、
「この仲間のために」というチームとしての一体感、
困難な状況での創意工夫、
劣勢でも自分を見失わないメンタリティ、
これらも加味されて、勝負強さが増してきます。
筆者は今回の慶応高校野球部の成果を以下のようにとらえています。
「人間が本来持っているエネルギーを適切に発露させることによって、成果につながる」
いわゆる「エンジョイ・ベースボール」です。
これは企業活動についても全く同じことが言えます。
今、企業では、ハラスメント、メンタル不調、仕事への意欲の低下などが大きな問題になっています。
なぜならそれが成果の大きな妨げとなっているからです。
一人ひとりが本来持つ力が発揮されていないわけです。
・業績至上主義
・そこで働く人たちが、自分の思いや考えを聞いてもらえない(一方通行の指示)
・時代に合わないルールや慣習が数多存在している
高校野球に置き換えれば、
・勝利至上主義
・指導者の言うことが絶対で、部員はそれに従うだけ
・何のための坊主頭か?
ということになります。
これらは、人間が本来持つ「成長ホルモン(=主体性・自発性・意欲)」を減退させます。
組織において「成長ホルモン」を適切に分泌させるには、以下のことが大事になってきます。
外的要因(自分以外の問題)として、
・「組織の目的」への共感
・自分の意見や考えを表現できる場があり、それを聞いてくれる人への信頼感
・自己成長に対する適切なフィードバックを受けられる、成長実感
内的要因(自分自身の問題)として、
・自己目標・自己ビジョンの設定
・自己成長に向けた自己規律(セルフマネジメント)
・チームに貢献するための振る舞い(他者の尊重・共感・許容)
僭越ながら、慶応高校野球部と当社の取り組みは、活動のフィールドこそ違えど重なりを感じています。
当社ミッション「人が活きる、組織が活きる、成果が実る。それが私たちの仕事。」を心の中心に据えて、より一層精進していきたいと思います。


