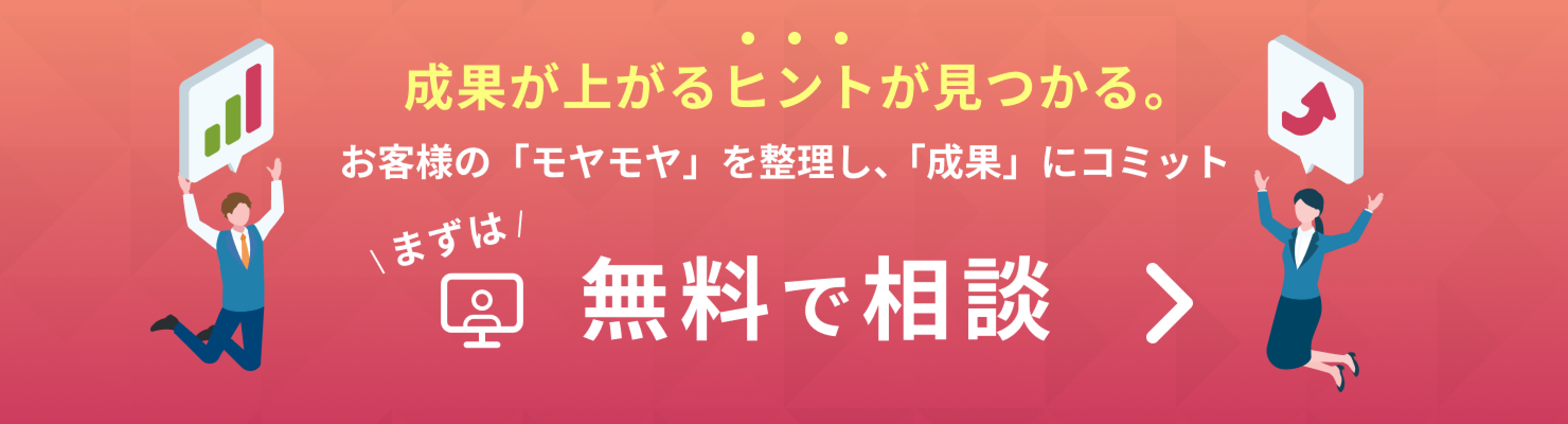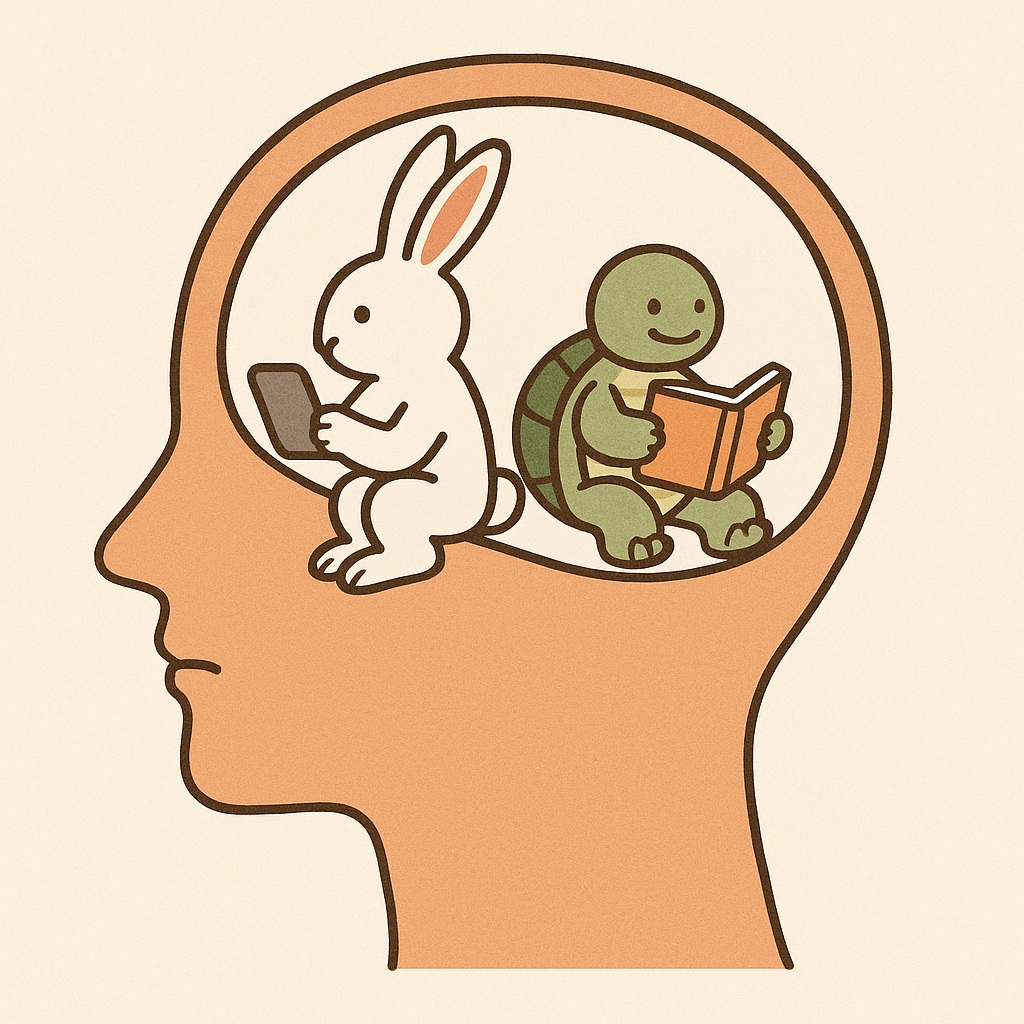更新日 2025.05.14
【第227号】「問い」のねじれ

サラリーマン時代、ずっと引っかかっていたことがあります。
「どうやって業績を上げるか?」という問いが、まるで呪文のように飛び交っていたことです。
会議でも、雑談でも、飲み会の席でさえも、数字、数字、また数字。
「数字がすべて」「利益が出ればOK」——そんな空気が、社内に当たり前のように流れていました。
なかには「お客様にバレなきゃ大丈夫でしょ」と言う人もいて、
心の中で「いや、それ、どうなんだろう…」とつぶやきながらも、うまく言い返せず、やり過ごしていた自分がいました。
ですが、今思い返しても、「明らかにおかしい」と感じた場面があります。
それは、修学旅行の企画・手配をしていたときのこと。
一生に一度の修学旅行の生徒たちに、自分が「これはおいしい!」と心から思えた弁当ではなく、
収益率の高い弁当を優先して売るよう指示されたときのことでした。
「こっちの方が利益が出るから」
そう言われた瞬間、怒りが込み上げました。
相手は、一生に一度の思い出を楽しみにしている学生たち。
「美味しい!」と笑ってくれる顔を想像しながら選ぶのが、本当の“仕事”なんじゃないか?
それを、自分たちの都合でねじ曲げるのか?と。
黙って従うこともできましたが、そのときは、指示に従わず、
「自分が美味しいと思った弁当」を手配しました。
「たしかに数字は大事かもしれない。でも、自分の良心を捨ててまで、数字に合わせたくない」
「数字に魂は売りたくない」——あのとき、心の奥でそう叫んでいた自分がいた気がします。
今になって思えば、あの瞬間は、“問いのねじれ”に気づきはじめた出来事だったのかもしれません。
「どうすれば業績を上がるか?」じゃなくて、
「どうすれば、お客様に心から喜んでもらえるか?」
仕事は、本来そこから始まるはずです。
もちろん、「どうすれば目標を達成できるか?」という問いが、常に間違っているわけではありません。
試験や資格のように、自分ひとりで完結するものにおいては、有効で力強い問いです。
ですが、仕事は違います。
そこには、必ず“他者”が関わります。
お客様、同僚、部下、上司。
そのなかで「自分の目標」ばかりを追いすぎると、
誰かを押しのけたり、無理をさせたり、守るべき価値をねじ曲げてしまうことがあります。
だからこそ仕事では、
「どうすれば、相手にとって価値あるものを届けられるか?」
という問いこそが、出発点になるべきだと、いまは思うのです。
いまの自分の軸も、そこにあります。
仕事は、「相手に価値を感じてもらってナンボ」。
ウソやごまかしは、いずれバレる。
いや、たとえバレなくても、自分にはバレています。
だから大事なのは、他人との競争じゃなく、「自分の妥協」との戦い。
昨日よりほんの少しでも、質のいいもの、価値あるものを届けたい。
そんなふうに働けた日は、どこか気持ちが晴れる気がするのです。
そんな筆者はいま、企業の“1on1”浸透支援の仕事をしています。
そして、あの頃と似たモヤモヤに、よく出会います。
たとえば、ある企業の人事部の方(=本社側)から、こう相談されました。
「制度として1on1を導入したのに、なかなか定着しないんです」
「制度は整えた。マニュアルも作った。なのに、現場が動かない」——
そんな歯がゆさを抱えておられました。
一方で、現場の社員やマネージャーに話を聞くと、返ってくるのはこんな声です。
「また新しいことが始まった」
「正直、何を話せばいいのか分からない」
「なんだか“やらされ感”があるんです」
このとき、筆者が強く感じるのが、
「もしかして、最初の“問い”を間違えていないか?」ということ。
本社は「どうすれば1on1を定着させられるか?」と考えている。
現場は「なんで急に1on1なんてやらされるの?」と戸惑っている。
ここには、問いのねじれがあります。
さらに残念なことに、多くのHR会社はこの“ねじれ”の根本を見ずに、
「動画を導入しましょう」「コーチングを入れましょう」と、
手段を“商品”として売り込んできます。
もちろん、動画やコーチングが悪いわけではありません。
でも、「現場が困っているのは、それがないから」ではないのです。
「なぜ1on1をやるのか?」「誰のためにやるのか?」
その問いを飛ばしたまま、どれだけ高価なパッケージを導入しても、現場には届きません。
付け焼刃で終わり、効果が出ないのです。
それでもHR会社側は、自社の売上に満足して終わる。
成果ではなく、数字を追う。
それはかつて筆者が感じた、「利益のために本質をねじ曲げる」構造と、どこか同じ匂いがします。
—— 数字に魂は売りたくない。
あのとき、修学旅行の弁当を選んだ自分と、
いま、現場と向き合っている自分は、同じ問いの上に立っています。
本来、立てるべき問いはこうです。
「どうすれば、上司と部下が信頼関係を築けるか?」
「どうすれば、社員がこの会社で成長していきたいと思えるか?」
1on1の導入や実施は、そのための“手段”であり、“目的”ではありません。
手段が目的化すると、「とりあえずやる」「とにかく回数をこなす」といった状態になり、
やがて、現場にとっての負担に変わってしまいます。
でも、人は“やらされている”と感じているうちは動けません。
「これは意味がある」「やってみてよかった」と実感したときに、初めて“自分ごと”になるのです。
ある上司の方が、こんなことを話してくれました。
「1on1を続けていくうちに、部下のことに関心を持てるようになりました」
「初めて、一緒に笑えた気がしました」
こういう「小さな実感」こそが、組織を少しずつ変えていく。
——あのときの弁当の選択と、どこか重なります。
相手の顔を思い浮かべながら、自分の正直さに従って選ぶ。
そんな小さな選択が、やがて信頼を生み、文化をつくっていくのだと思います。
最近では、「エンゲージメントを高めたい」「健康経営」という言葉もよく耳にします。
でも、それもまた「結果」であって、「目的」ではありません。
信頼できる関係があって、安心して働けるからこそ、心が整い、体も元気になる。
「エンゲージメントを高めよう!」「まず健康的に働こう!」と呼びかける前に、
立ち返るべき問いがあるはずです。
だからこそ、大事なのは——問いの順番。
業績向上ではなく、価値提供。
1on1の実施率ではなく、関係性の向上。
エンゲージメントではなく、信頼と対話の実践。
もし今、何かがうまくいっていないと感じているなら、
まずは自分が、どんな問いを立てていたかを、そっと見直してみる。
そこから、きっと何かが変わり始めるはずです。
少なくとも、筆者はそうやって試行錯誤しながら、今も歩いています。