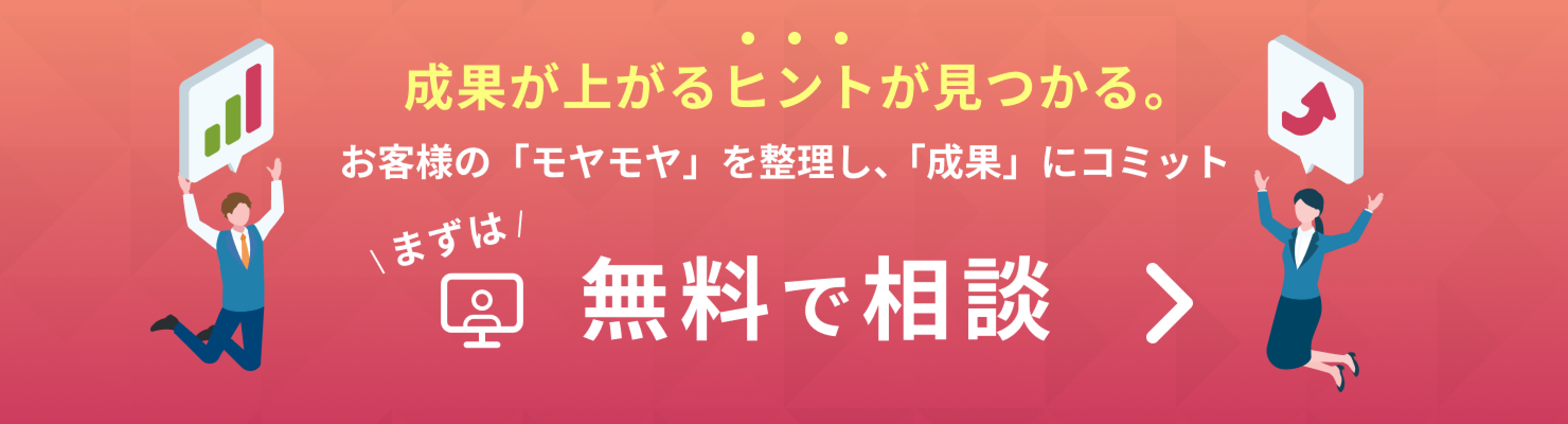更新日 2025.07.05
【第235号】「速い脳」と「遅い脳」~川島隆太先生との対話での気づき~
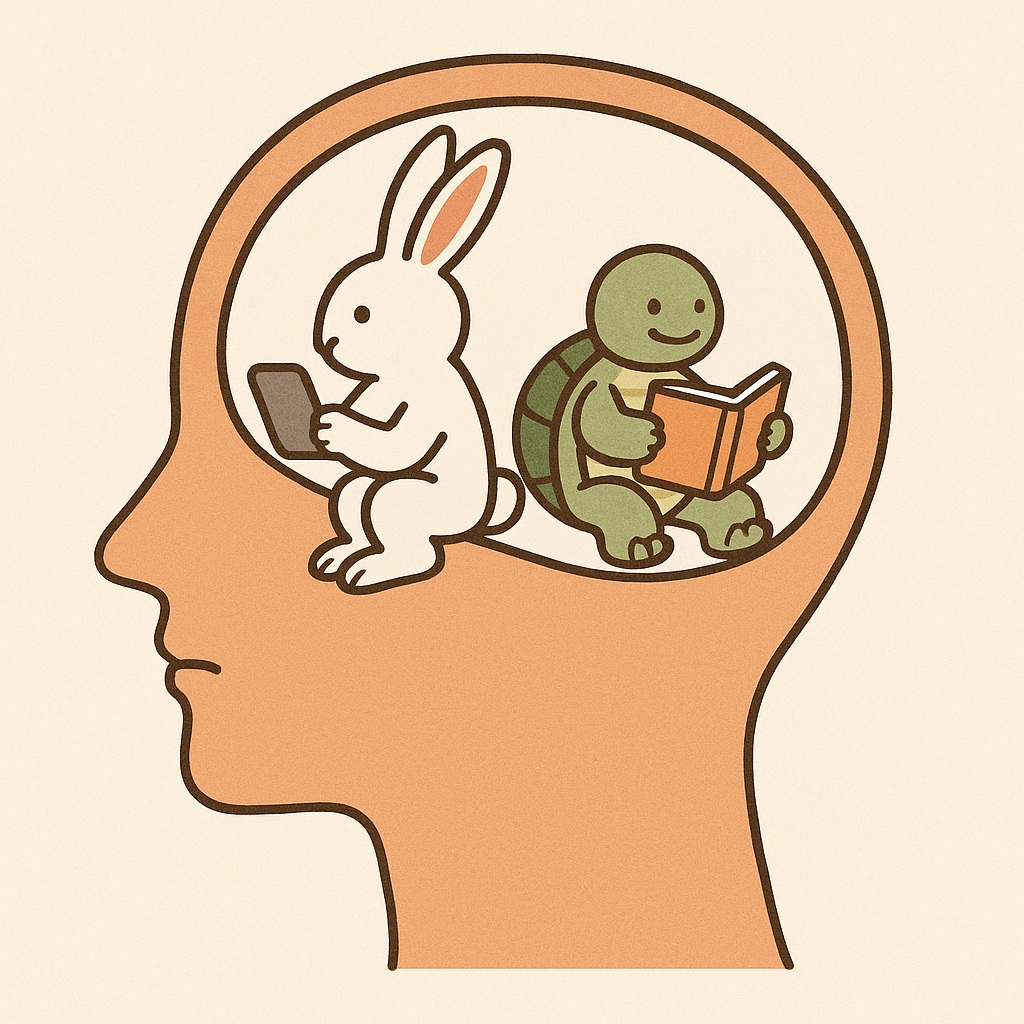
先日、当社の活動を応援してくださっている、任天堂『脳トレ』でお馴染みの川島隆太教授に会ってきました。
そこでの対話が、かなり腑に落ちる内容だったので、読者のみなさまにも共有したいと思います。
川島先生によれば、(あくまで便宜的な表現として)人間の脳には「速い脳」と「遅い脳」があるそうです。
スマホの普及によって、現代人はこの「速い脳」ばかりが優位になってしまっているとのこと。特に子どもたちは顕著だそうです。
先生は、ふとこんなこともおっしゃっていました。
「これからの管理職は大変ですよ。すぐジャッジする、シャッターを下ろす、集中が続かない子がこれからどんどん社会に出ていきますから」
この言葉に、思わずうなってしまいました。
たしかに最近、「すぐに答えを求めたがる」「すぐ会社を辞める」「“ながら聞き”をする」――そんな若手の姿を見ることが増えたように思います。
「速い脳」とは、直感的に判断したり、瞬時に反応したり、本能的・短期的に物事を処理する脳の働きです。
これは決して“悪い”ものではありません。
危険を察知してすぐ避ける、瞬時の判断で物事を進める…生きていく上で必要不可欠な能力です。
ただ、問題はこの「速い脳」が優位になりすぎると、「すぐに決めつけてしまう」「相手をジャッジしてしまう」「待てなくなる」といった、コミュニケーション上の“副作用”が出てくることです。
自分自身のことを振り返っても、いつの間にかそうした反応をしていたことに、ハッとさせられました。
さらに川島先生は、こうした傾向の背景には、経済的な構造もあるといいます。
たとえば、広告やSNSは「速い脳」を刺激した方が、感情的に“買いたくなる”仕掛けを作りやすく、「消費」につながります。
それに伴い、テック企業は「即時性(リアルタイム通知)」「即決(1クリック購入)」「直感操作(スワイプ)」など「速い脳」を刺激する設計をあえてしています。
つまり、社会全体が「速い脳」を酷使する方向に流れていくのは、ある意味で必然なのです。
ですが、私たちは本当にこのままでいいのでしょうか?
むしろ今こそ意識的に、「遅い脳」を取り戻す必要があるのではないか。
そう強く感じました。
「遅い脳」とは、多角的に物事を考えたり、思慮深く判断したり、「すぐに白黒つけない」脳の働き。
たとえば、人の意見をまず受け止めてみる、自分の感情を俯瞰する、違和感を咀嚼する…といったプロセスは、まさに「遅い脳」の出番です。
そして、私たちが提供しているコーチングは、この「遅い脳」を使うためのコミュニケーションです。
人を“判断”するのではなく、相手の話を“待ち”、寄り添い、対話を通じて関係性を築いていく。
まさに、効率や即答が重視される現代に逆行するようでいて、本質的に求められている“人間らしさ”なのだと思います。
そして今、あらゆる人間関係の問題──
「話が噛み合わない」「すぐに否定される」「誰にも理解されない」
といった悩みの根っこにあるのも、もしかしたら、“お互いが「速い脳」のまま向き合ってしまっている”からではないか?
だからこそ、「速い脳」を緩め、「遅い脳」でつながる時間を意識的に持つこと。
それが今の時代に必要な“人との向き合い方”なのかもしれません。