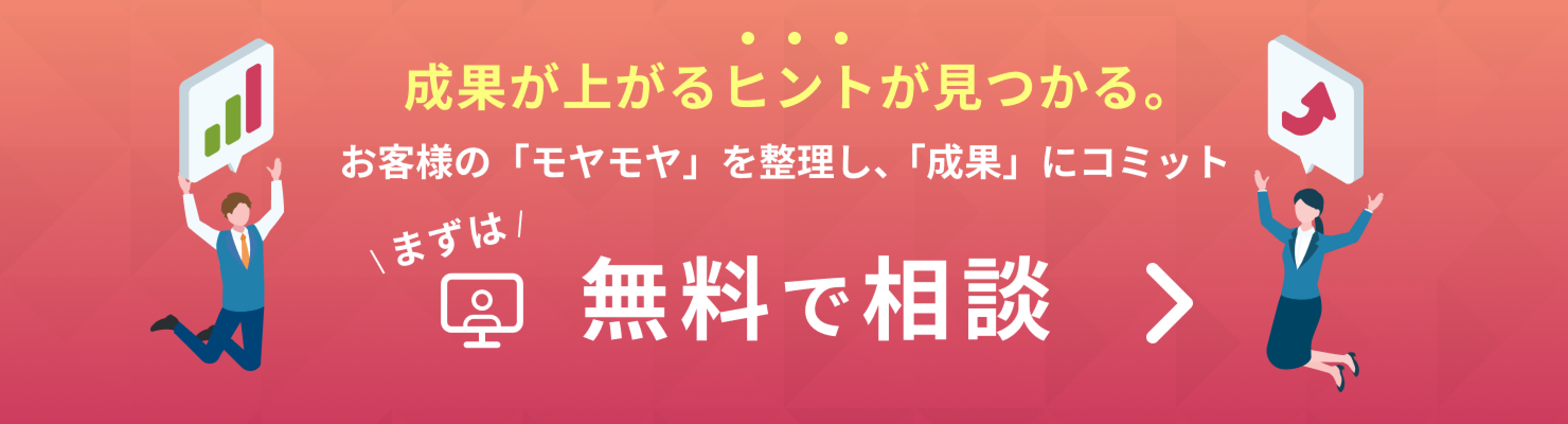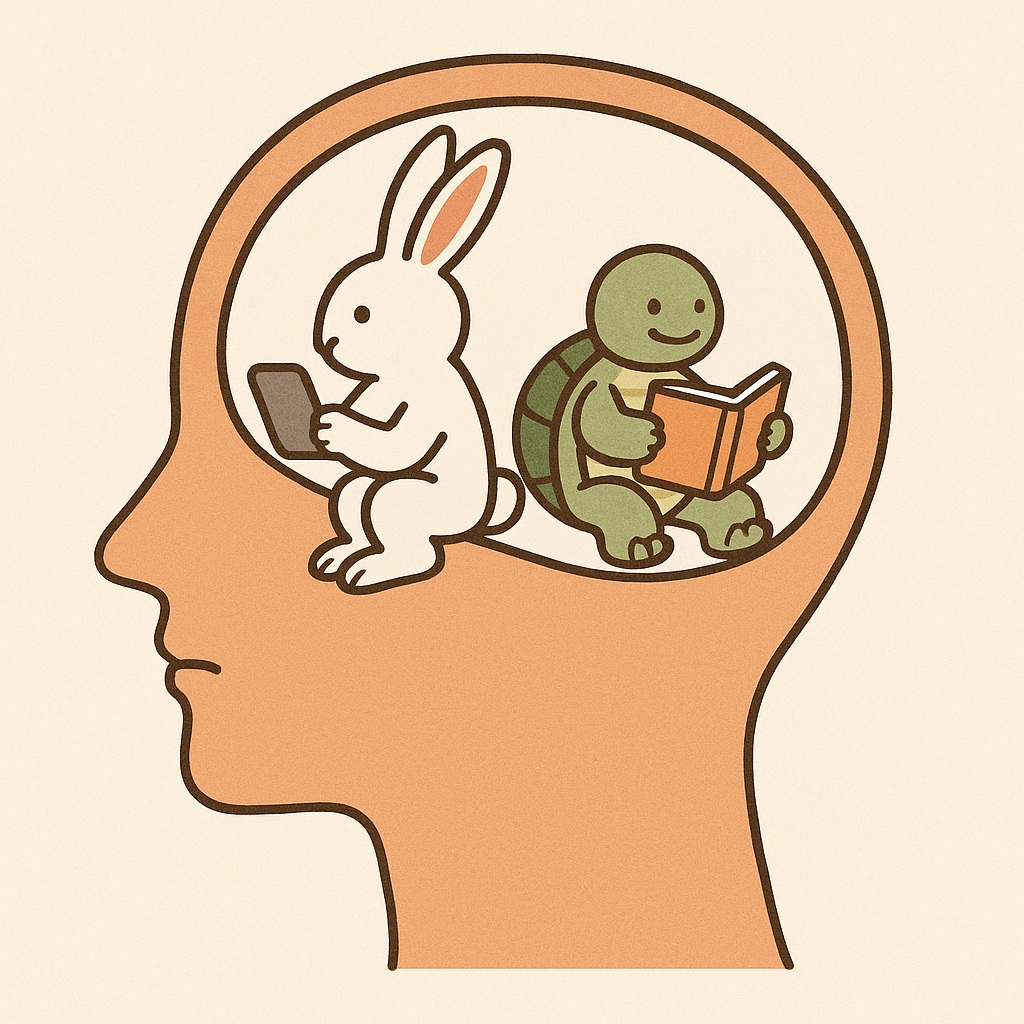更新日 2025.05.25
【第229号】見切らない力 ~「リセット社会」に染まらないマネジメント~

企業管理職向けのマネジメント研修を実施していると、必ずといっていいほど聞かれる声があります。
「部下が成長しない」「教えても反応がない」「即戦力を採用した方が早い」——
そんな声を、マネジメントの現場で耳にすることが増えてきました。
その気持ちには、筆者も強く共感します。
一方で、どこか胸の奥に引っかかるものもあります。
成果を出すスピードと効率を求められるハードルは、年々高まっています。
ですがその一方で、人と向き合い、信頼を築き、成長を促すには、どうしても時間がかかる。
この“時間軸の矛盾”こそが、
現代の「人」のマネジメントを最も難しくしているのではないかと感じています。
うまくいかないとき、人は「関係をリセット」したくなります。
- 無反応な若手に、なるべく関わらない
- 変わらない人に、極力時間を割かない
- わかってくれる人だけと、仕事をする
この“切り捨て”や“見切り”の早さは、今の社会の空気をそのまま映しているように思えます。
「リセット社会」が加速していると感じるのは、筆者だけでしょうか。
- SNSでは、気に入らなければ即ブロックやミュート
- 仕事では、成果が出なければ交代・配置転換・早期見切り
- 組織でも、カルチャーが合わなければ転職が当たり前
- アプリも、モノも、人間関係すらも、何度でも“やり直せる”世界
そんな便利な世界の裏側で、
「関係を続けること」や「積み重ねること」の価値が、見えづらくなっている気がします。
ある調査では、若手社員の多くが
「自分はすぐにジャッジされ、ラベルづけされていると感じる」と答えています。
また別の調査では、育成がうまくいかない理由に、
「上司が結果重視・即戦力偏重になりすぎていること」が挙げられていました。
これは、誰か一人の問題ではなく、
“成果を急がせる社会”と“人間関係の時間コストを避けたがる風潮”が生んだ、構造的な課題かもしれません。
ここで一つ、語源の話を紹介させてください。
「マネジメント(management)」という言葉は、
もともと「馬を手綱でうまく扱う」ことを意味していたそうです。
思い通りにならない生き物を、無理やりコントロールするのではなく、
共に進んでいくための“手綱さばき”の技術。
つまりマネジメントとは、
「不確かさと共にありながら、人を導いていく営み」なのです。
そう考えると、人がすぐに変わらないことや、育成に時間がかかることは、
むしろマネジメントの“本質”そのものなのかもしれません。
筆者もこの1年、マネジメントの現場で多くの壁にぶつかってきました。
だからこそ、強く思います。
「人」をマネジメントする力とは、短期的にも高い成果を求められる一方で、
「時間軸の矛盾を受け入れ、リセットせずに向き合い続ける力」ではないか、と。
成果が出るかは、わからない。
相手が変わるかも、今は見えない。
それでも、関係を投げ出さず、問い続け、関わり続ける。
それは、非効率で、面倒で、報われないことも多いかもしれません。
けれど、その非効率のなかにこそ、人が育ち、信頼が芽吹く土壌があるのだと信じています。
筆者自身、怒ることもあるし、愚痴もこぼします。
「もう関わりたくない」と思う日も、正直あります。
それでも今は、自ら関係を絶たないように、心がけています。
- 怒ることもある。でも、見切らない。
- ぼやくこともある。でも、種まきはする。
- 呆れることもある。でも、関与し続ける。
この感情と責任のあいだの葛藤のなかで、
少しずつ、自分の器が広がっているのを感じます。
そして、ふと思うのです。
自分もかつて「誰か」に、そうしてもらったのだと。
叱られ、迷惑をかけ、呆れられたことも何度もありました。
それでも、見捨てられずに、向き合ってもらえた。
その関係に、何度も救われてきました。
人をマネジメントするということは、
誰かを変えることではなく、
“あのとき支えてもらった何か”を、次の誰かに渡していくこと。
それは、リセット社会に流されず、
人間として生きていく覚悟の現れなのかもしれません。
これから、ますます多様な価値観が交錯する時代になります。
自分とは前提の違う相手と働くことも、どんどん増えていくでしょう。
だからこそ、「切らない」「向き合い続ける」という覚悟が、
これからの社会では、最も“希少で価値ある力”になっていくと、筆者は確信しています。